
多様な主体の協働で進められる、岡山市の社会課題解決の取組を表彰する「おかやま協働のまちづくり賞」。「笑顔」「場づくり」をテーマに募集された第1回は、20もの素晴らしい取組がエントリー。2017年2月19日(日曜日)、Junko Fukutake Hall(岡山大学鹿田キャンパス内)にて最終審査が行われ、5つの入賞取組のプレゼンテーションの後、「岡山市協働推進委員会」による審査と参加者の投票により、「病気の子どもたちが安心できる居場所づくり」が大賞に選ばれました。
第1次審査でファイナリストに選出された5つの取組のプレゼンテーションは次のとおり。いずれも協働の工夫や課題解決への情熱にあふれ、参加者からは、すがすがしい学びのある発表だったと、感動の声が多くもたらされました。
ファイナリスト5つの取組の最終審査
さいさい子ども食堂 さいさいサポーター
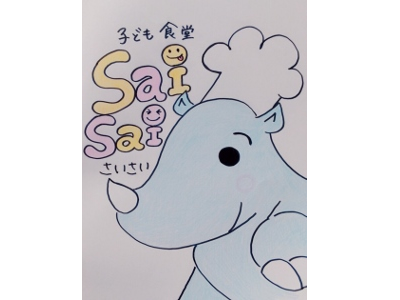
さいさい子ども食堂 さいさいサポーターのページはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く
毎月第2土曜日を基本に、地域の子どもたちに昼食を提供している「さいさい子ども食堂」。
「地域の子どもは地域で育てよう」という方針で、孤食や子どもの貧困問題の解決に取り組みました。会場として特別養護老人ホームの協力があったほか、食事だけでなく日用品の共有が行われたり、食材を提供してくれる協力者も集まったりするなど、コミュニティをあげての活動となっています。
田中純子審査員のコメント(京山公民館)
子どもの笑顔があふれて心があたたかくなりました。地域の課題を活動に繋げたのが素晴らしいと思います。
宇野学区放課後宿題教室 宇野学区コミュニティ協議会

宇野学区放課後宿題教室 宇野学区コミュニティ協議会のページはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く
宇野小学校の中に設置されたコミュニティハウスを活用し、火曜日と金曜日の放課後、子どもたちの学習支援を行っている。地域住民や学生など総勢約20名のボランティアが交代で参加。勉強を教えるのではなく「宿題をすること」を見守り、宿題をすませる習慣を身につけていく場に。子どもたちの「ただいま」にボランティアスタッフが「おかえり」と答えるなど、学習支援以上のあたたかい交流も。子どもたちが「地域」を実感できる取組となっています。
岡山一郎審査員のコメント(株式会社山陽新聞社)
地域と学校を組み合わせた事業として、他のモデルとなる取組だと感じました。ボランティアとして活動する地域の高齢者の皆さんにとっても生きがい作りになっていると思います。
キッズフェスティバル NPO法人岡山市子どもセンター

キッズフェスティバル NPO法人岡山市子どもセンターのページはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く
「子どもの遊び欲求を刺激するような楽しい遊びの場の提供を」と、2001年から継続的に開催されている「キッズフェスティバル」。
ボランティアスタッフの養成も丁寧に行われ、子どもや子どもの遊びへの理解を深め、当日に臨んでいます。参加した子どもが後にボランティアとなるなど、良い循環ができているのも特長です。吉田万里子審査員のコメント(岡山市立吉備中学校)
子どもたちの笑顔で幸せな気持ちになりました。外遊びの機会の減少が懸念されている現代社会において、先駆的な取組を16年も継続されていることは素晴らしいと思います。
病気の子どもたちが安心できる居場所づくり NPO法人ポケットサポート

病気の子どもたちが安心できる居場所づくり NPO法人ポケットサポートのページはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く
岡山大学病院内において、病気の子どもたちが抱える不安やストレスを少しでも軽くし、前向きに治療に取り組めるよう、学習支援や交流イベントを行う取組です。入院から復学までの期間、教育を受けられない「ポケット」にいる子どもたちに、患者としてではなく、ひとりの子どもとして等しく学ぶ場を提供しています。
松井圭三審査員のコメント(中国短期大学)
初めてこの取組を知りましたが、一人ひとりを社会に取り込む「包摂社会」という言葉を思い出すような、優しい社会を作る活動だと思いました。
横井の夢広場「わくわく農園」 よこいゆめくらぶ

横井の夢広場「わくわく農園」 よこいゆめくらぶのページはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く
急速に都市化が進んだことで増えた耕作放棄地を有効活用し、地域の子どもたちに農業をする機会を提供する活動。
農業を体験した子どもたちの心の成長、地域住民同士の交流や地域への愛着など、さまざまな効果を生んでいます。まさに「ALLよこい」で行っている取組といえます。
岩淵泰審査員のコメント(岡山大学地域総合研究センター)
人の助け合いがないとできない活動。子どもを巻き込むことで地域課題の解決を目指す姿勢に感動しました。横井の子どもたちは幸せだなあと感じます。
質問・交流タイム
プレゼンテーション終了後は、質問・交流タイムです。展示ブースは、参加者からの感想・質問が書かれた付箋でいっぱいに。意見交換や質問をするだけでなく、「自分も活動に参加したい」という声も出るなど、充実した時間となりました。

展示ブースでの付箋によるコミュニケーション

質問・意見交換も活発
表彰式
審査が終わり、いよいよ大賞の発表・表彰式に移ります。
岡山市議会の小林副議長から、「それぞれの地域がそれぞれの課題と向き合い取り組むことで、地域への愛着が湧き、本当の地域振興が生まれるのだと思います」と祝辞をいただいた後、田上和彦審査委員長から大賞を発表。第1回協働のまちづくり賞の大賞を受賞したのは、「病気の子どもたちが安心できる居場所づくり」。大森雅夫岡山市長から5つの取組すべてに表彰状が手渡され、会場はあたたかい拍手に包まれました。
田上和彦審査員長(日本政策金融公庫岡山支店)

「ファイナリスト5つとも子どもに関する取組となりました。社会課題や未来を考える中で、次代を担う子どもにスポットが当たったのだと思います。課題解決に取り組んでいる皆さまに敬意を抱くとともに、こんなに多彩な取組がある岡山を誇りに感じました。大賞の取組は、笑顔になりにくい病気の子どもたちを笑顔にする活動です。これまで支援が届いていなかったところを協働により支援しているのが素晴らしい。今後、協働がさらに根付いていくことを期待しています。」
大賞受賞取組(代表団体理事三好祐也さん)

「5歳から病院で過ごした自分の経験からはじめたこの活動。共感し、協力してくださった病院・行政の皆さんの力で受賞できました。これをきっかけに、子どもたちの笑顔がもっと増えると良いなと思います。」
大森雅夫岡山市長祝辞

「受賞者の皆さんに、『おめでとう』ではなく『ありがとう』を贈りたいと思います。岡山のまちを良くしよう、支えようとしてくれる皆さんは、市民の鑑だと思います。ただ、社会課題に無関心な層も多く、会場にお越しいただいた皆さんが、口コミで関心を広げていくことも大切だと思います。」
NPO法人ポケットサポート代表理事 三好祐也さんにお話を伺いました!

「病気の子どもたちが安心できる居場所づくり」に関わった皆さん
「率直にうれしい気持ちです。10年コツコツ続けてきましたが、この協働のまちづくり賞へのエントリーをすることで、色々な人に話を聞いてもらう機会ができました。ぼくたちの取組は、医療と教育のまち岡山だからこそ、多くの方にご協力いただき、実現できたモデルだと思います。今後は、岡山大学病院だけでなく、他の病院とも協働し、もっと活動範囲を広げていきたいです。活動をもっと知ってもらうことで、応援してくれる人が増えていく。それが子どもたちの笑顔・居場所につながれば最高ですね」
発表・展示の5つの取組の皆さまをはじめ、エントリーをいただいたその他15の取組の皆さま、インターネット投票をいただいた皆さまなど、多くの人の思いがつまった協働のまちづくり賞の最終審査は、協働を学び、未来を考える、熱いフォーラムでした。司会の小倉恵美さん、音楽の岡本方和さん、素敵な看板を作っていただいた岡洋子さんと「ありがとうファーム」の皆さん、花で会場を彩ってくれた「ももぞの福祉園」の皆さん、数多くの皆さまの力であたたかい一日となりました。
これからも、毎年テーマを変えて、「協働のまちづくり賞」は続いていきます。

これからもっともっと素敵な協働の取組が増えることを、のっぷは楽しみにしているよ!
