ESD・市民協働推進センターは「岡山市協働のまちづくり条例」第8条に規定された協働のコーディネート機関です。名前に「ESD」がついている意味をよく聞かれます。持続可能な発展のための教育「ESD」の市民活動への浸透・普及の一端を担っているのがその主な理由ですが、協働という手法の推進は持続可能な地域づくり、社会づくりのためにとても有効な手法であり、条例では、協働の推進により「活力ある持続可能な地域社会の実現」を目的として掲げています。
そのため、当センターの事業の柱のひとつが「ESDプロジェクト普及促進事業」です。ESDに取組む市民団体の発掘や取り組もうとする活動の支援をすることで、市民活動へのESDの広がりをめざしています。2017年10月21日に岡山ESD推進協議会が主催した「ESDフォーラム/ESDアワード2017」の当日の運営のお手伝いなどもさせていただいています。
- フォーラムの詳細は、ウェブサイト「おかやまSDGs・ESDなび」からもご覧いただけます。
日常的には、岡山ESDプロジェクト参加団体登録や、活動支援助成金申請の相談も受けています。岡山地域(岡山市及びその周辺)において市民のために幅広くESDを推進する市民団体や教育機関、公民館、企業など参加団体は2017年12月現在274団体にものぼります。
つい先日も、ご相談に来られた団体さんがおられましたのでご紹介します。
今回ご相談に来所された皆さんは、今年の4月に子育て支援や子どもたちの体験活動を行う団体を発足される予定で、岡山ESDプロジェクトへの参加も希望されていました。
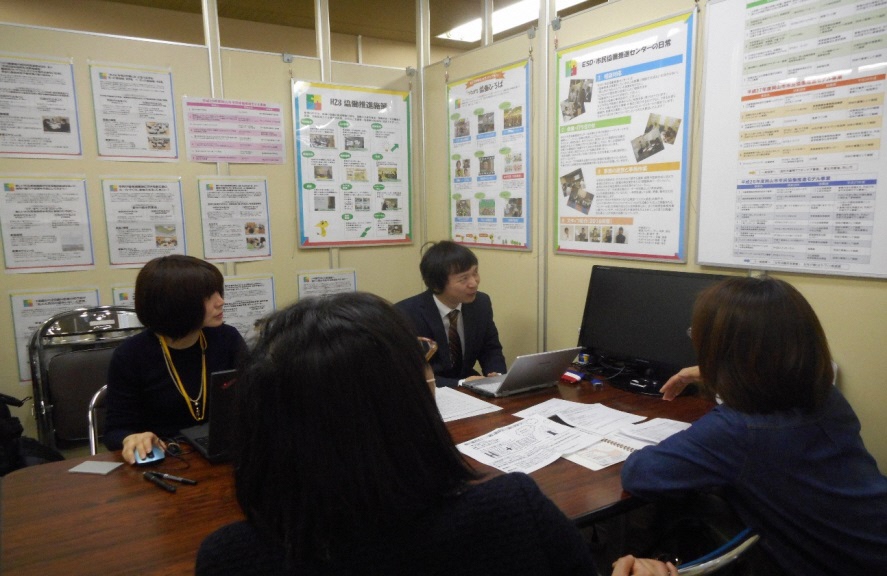
ESDプロジェクトの登録の方法や助成金の申請方法など説明しました
プロジェクト参加団体登録申請の相談を受ける時、申請に至るまでの方法や添付書類についてもご説明をしますが、まずは課題意識や解決に向けての活動内容、今後の展望などじっくりと聞かせていただき、内容と岡山ESDプロジェクト基本構想とがどのように関連しているかを一緒に確認を行っています。
ご相談の皆さんの課題意識は、核家族化、少子化など社会環境の変化の中ですすむ子育ての孤独、「孤育て」をしている母親たちの存在と、ゲームやスマートフォンの普及による子どもたちの「コミュニケーション力」、「考える力」、「感じる力」の低下でした。
「参加される親子や運営スタッフが一緒に主体となった自然体験活動や創作活動をやっていきたい、活動を通して地域とのつながりを深くし、親が子どもを安心して育てられ、子どもたちが健やかに成長できる環境づくり、社会づくりすすめていきたい」と力強く話してくださいました。
申請手続きとともに、団体規約や役員名簿の作成など、慣れない初めての作業に戸惑いも感じられたようですが、今回改めて「孤育て」の現状打開、親子の成長や変化など課題意識や活動内容を明確にし、加えて申請への疑問を解消することで、乗り越えてくださると思います。また、同じ課題意識をもって活動している他の市民団体や公民館など、岡山ESDプロジェクトの参加団体とのつながりが、さらなる活動への広がりや意欲の高まりにつながるのではと思います。
申請手続きのお手伝いをすることを通して、私自身もこうした持続可能社会づくりのお手伝いをさせていただいていると思っています。みなさんと一緒に持続可能な社会づくりを考え、学び、実行できるセンタースタッフとして、頑張りたいと思います。
