
操明学区連合自主防災会
目指す目的
地域防災の最前線で活動する「防災共助員」を町内会単位で発掘し、要配慮者支援の充実、学校・企業との連携を強化し、子・孫の代まで持続可能な防災組織の構築を目指す。
主な実施事業
- 人材の発掘と各組織の連携強化
- 要配慮者名簿の更新
- 一時避難所の円滑運営マニュアル作成
- 防災アンケート配布・集計、ほか
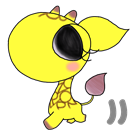
2016年9月25日(日曜日)に、ふれあいセンターで開かれた操明学区連合自主防災会による「連合役員会」におじゃましてきました。

連合役員会の様子
約1か月後に本番を迎える操明学区防災訓練に向け、約20名の各団体役員が集まりました。訓練当日の流れ、トランシーバーの使用方法確認、要配慮者名簿の取り扱い方、避難所となる操明小学校の運営方法、各団体の役割のなどを協議し、決めていきました。
特にトランシーバーを利用する事で、誘導班、消火班、救出救護班などの横の連携がスムーズに運び、地区の社会福祉協議会や小学校などの各団体同士の連携もうまくいきそうです。非常時の情報の共有はとても大切な事ですね。
リーダーとなって活動されている方々の世代は様々で、若い方が経験豊かな方たちから過去の情報をもらいながら、新しい形を作っています。世代を越えてみんなで協議を繰り返した訓練は、11月3日(木曜日・祝日)に本番を迎えます。訓練に参加することで、学区の皆さんの防災意識はさらに高まるでしょう。

世代を超えて、学区全体で防災活動に取り組んでいるんだね。
この事業のここに注目!
事業の伴奏支援を行っているESD・市民協働推進センターより、この事業の特に注目すべき点や応援メッセージをご紹介します。
5か年計画の2年目となりましたが、地域住民を各専門班(救護班・情報班・受付班など)に配置してトランシーバーで情報を共有しながら行う大規模な避難訓練には約500名が参加されており、住民参加の促進、リーダー育成、多様な主体との協働などの面で効果が見え始めています。反復訓練だけでなく、ルールやマニュアル整備を同時に進行することは大変な苦労が想像されますが、他地域へノウハウと勇気を届けるために残りの計画期間も着実に事業を進めていただきたいと切に願います。
