社会のため、未来のために活躍する「若い力」に注目し、そのチャレンジを紹介するコーナー「YOUTH CHALLENGE」。
今回は、岡山大学環境部ECOLOについてご紹介します。
なお、内容は取材当時のものです。
岡山大学環境学部ECOLOとは?
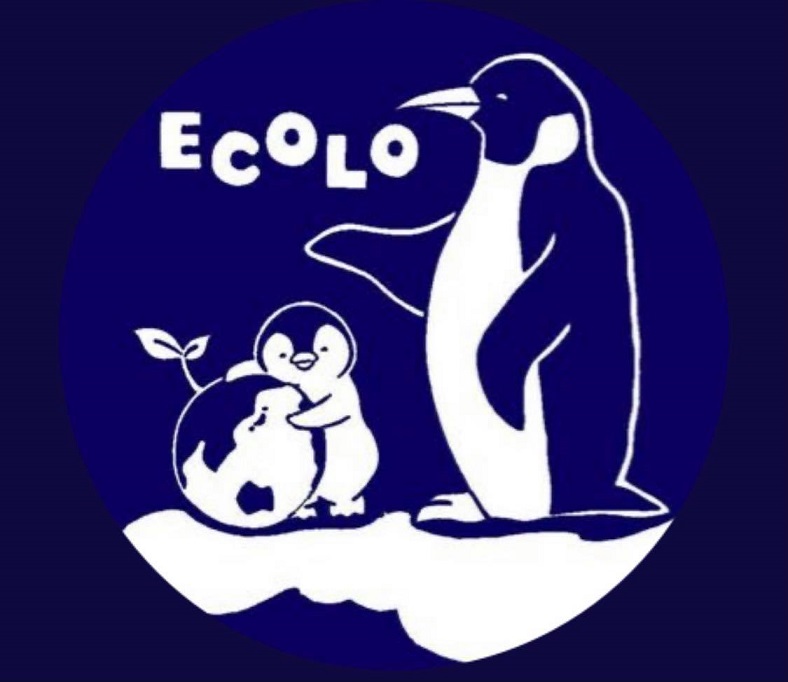
ECOLOロゴマーク
「岡山大学環境部ECOLO」(以下ECOLO)は、環境に興味・関心がある学生を中心にした岡山大学校友会認定の団体です。
学内外で「環境」に親しみを持てる様々な活動を行っています。
現在の部員は約20名。
もともと、専攻が環境系のメンバーが多かったECOLOですが、近年では工学部や文学部といった多様な学部のメンバーで構成されています。
まだ使えるものを必要な人へ届ける「リサイクル市」
まだ使えるものを無駄にせず、資源を有効活用することを目的として、毎年ECOLOが主催しているのが「リサイクル市」です。
卒業する先輩から家具・家電を引き取り、汚れを綺麗にしたり、家電の動作確認を行った上で新入生や留学生へ格安で提供します。
毎年、約300点もの家具・家電が集まり、そのうち9割以上は引き取り手が見つかります。
ごみを減らし、必要な人に届けるこの仕組みは、2001年から行われており、ECOLOの活動にとって大きな柱となっています。
購入するのは多くが新入生、留学生です。
特に留学生の場合、家電量販店での購入は文化や言語の壁があるためハードルが高く感じています。
その点「リサイクル市」で一式を揃えることができれば、安心して日本の学生生活をスタートできるメリットもあるようです。

依頼があれば、回収や配送も行います

回収した家具・家電が並べられた様子
実際の活動では軽トラックをレンタルし、家具・家電の回収のために卒業生宅をメンバーが訪問します。
1日に10件から20件、回収した家具・家電を整備するのもECOLOのメンバー。
清掃から動作確認まで行ったうえ、リサイクル市で販売し、依頼があれば購入者の自宅へお届けするサービスまで行います。
「回収、清掃、販売、配送を全てECOLOのメンバーで行うので、運営には労力がかかりますが、まだ使えるのに粗大ごみになってしまうのはもったいない。という思いで実施しています。ECOLOで買った家具や家電を長く使っているという話を聞くと役立っていることが実感できます。」(部長の串田さん)
新しい知識を共有する「環境学習」
ECOLOでは月に1回、メンバー間の情報共有のため定例会議を行っています。
コロナの影響で長らくオンラインでの実施でしたが、6月からはオンラインと対面の両方で行っています。
定例会議では、事務連絡や情報共有のほか、2021年から環境について調べたことを共有する「環境学習」を始めました。
部員のなかで担当を持ち回り、興味をもった環境問題について発表し、意見交換をします。

メンバーの発表を聞き、意見交換をしています
取材時のテーマは「バイオ燃料はなぜ日本では普及しないのか」。
海外の普及事例をもとに、燃料の原料となる菜の花の栽培環境など土地柄の問題から、家庭ゴミとなる天ぷら油の燃料転用について、その課題点などの意見があがりました。
勉強会では、テーマの決まりはなく、新しい知識の共有や身近な環境問題について知るきっかけになっています。
楽しみながら環境を守ろう
ほかにも、ECOLOでは身近なところから環境を守る取組みを実践しています。
例えば、古紙回収ボックスを岡山大学図書館に設置をし、古紙のリサイクルを呼びかけています。
テスト期間終わりは特に多く集まり、15kgほどの古紙が集まります。
回収した古紙は、ECOLOのメンバーで束ねた後に図書館へ渡し、リサイクルに回されます。

回収した古紙を集まった部員で束ねる作業中

西川沿いのゴミ拾い
地域のイベントにも参加しており、京山地区のSDGs・ESD活動として、年2回、春と秋に行われる「環境てんけん」のイベントに参加して、小学生と一緒に地区の水質や大気を調べたり、川魚を観察したりして、環境調査を行います。
大学と地域がつながるとても良い機会になっています。
また、月1回の活動として、岡山駅前や西川沿いのゴミ拾いもしています。
1時間ゴミ拾いをするだけで煙草の吸殻やお酒の缶などでゴミ袋がいっぱいになります。
どの活動もみんなで話をしながら和気あいあいと実施しています。
ECOLOでは、環境を守るアクションが続くよう、楽しく継続していくことを大切にしています。
「仲間で集まって作業することがなにより楽しいですね。」と部長の串田さんは語ります。

ECOLOのメンバー

まだ使えるものを必要な人へ届ける「リサイクル市」は、売り手・買い手・環境にとってやさしい仕組みだね!
持続可能な社会を目指して、のっぷも環境にやさしいことを楽しく生活に取り入れてみるよ。
なお、「YOUTH CHALLENGE」では、「取材にきてほしい!!」という若者の取組を募集中です。
希望される方はお問い合わせフォームより、団体名、活動の内容を添えてご連絡ください!
