
実施団体
第二藤田学区大規模災害対策委員会
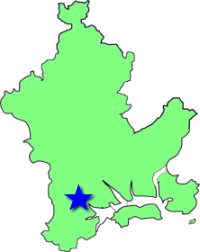
実施学区
南区 第二藤田小学校区
課題と目的
干拓地である藤田地域は海抜0メートル地帯で、大規模災害時には浸水・液状化・津波などの甚大な被害が予想されます。こうした大規模災害に備えて備蓄や一次避難施設を拡充すること、自主防災組織の拡大することが求められます。
大規模災害等の発生に対応できるように地域の体制を整備し、学区内住民の防災意識の向上をはかることで、安全安心な地域づくりの推進を目指します。(継続5年目)
事業実施内容
- 避難場所開設訓練
(9月19日:初期消火・搬送訓練・災害用伝言ダイヤルの使用体験など) - ウォーキングと炊き出し・防災訓練
(3月20日:簡易担架の作り方、ジャッキUP体験、健康チェック、災害伝言ダイヤルのデモ体験、簡易炊飯説明、河川敷ウォーキング、簡易おにぎり作り、非常食のお渡し) - 学区内各町内会の自主防災会の結成促進
防災訓練や町内会全体の会議などの機会に自主防災会の結成を促したが、新たに発足した会は無し。現在の結成率は単位町内会全体の半数程度である。 - 防災資機材の整備や備蓄
現在、非常用の食糧600食の備蓄や、テント、テーブル、発電機、簡易トイレ内の立ち上がり補助手すりや衛生用品の充実、簡易テントなどを整備している。非常食も賞味期限が近づくなど、新たな課題も明らかになってきた。 - 町内会単位の防災リーダー育成のための各種研修
予定していたが、コロナ感染状況の拡大により、延期の後中止となった。 - 学区内危険箇所点検と対策の検討、緊急避難場所確保
コロナ禍で危険箇所の点検は実施できなかった。緊急避難場所については、市や企業への問合せなどを行ったが、新たな緊急避難場所の確保には至っておらず、引き続き検討する。
資料
のっぷの取材レポート
令和3年9月19日(日曜日)に、南区錦第五遊園地で「防災訓練」が行われました。

第二藤田学区大規模災害対策委員会による「防災訓練」が行なわれました。「災害はいつ何時襲ってくるかわかりません。こんな時だからこそ、感染症対策を万全にし、出来る限りの訓練を行います。」と遠藤連合町内会長が力強く挨拶をされていました。
消火器での初期消火、リヤカーを使った搬送訓練、災害用伝言ダイヤル体験などの訓練に、参加された方々は「なるほど!実際にやってみて勉強になったわ!」と口々に仰っていました。言葉を交わさなくても住民同士の元気な顔を見れただけで、みんなが笑顔になっていきました。防災訓練を通してコミュニティが維持されているのを感じます。
令和4年3月20日(日曜日)に、おおすみせせらぎ公園周辺で「第9回『どんぶらこの里』ウォーキングと炊き出し・防災訓練」が行われました。


「第9回『どんぶらこの里』ウォーキングと炊き出し・防災訓練」では、災害時に役立つ簡易担架作りや瓦礫の下敷きになった人の救助のためのジャッキアップの練習、健康づくりのための血圧・骨密度チェックコーナーの運営など、盛沢山のプログラムが実施されました。
災害用伝言ダイヤル「171」の体験では、参加者から「これは練習しておかないと、いざという時迷うね。実際にやってみたから、よくわかって良かったわ~。」との声が聞かれました。
後半は、少し肌寒い風が吹くなか、川辺に咲いた河津桜を見ながら元気にウォーキングをして体力づくりと交流を行いました。河川敷公園を往復してスタート地点まで戻ってくると、おいしいご飯が待っています。紙コップを使った簡易おにぎり作りの体験を通して、災害時の節水炊事を学びました。
健康づくりと災害時に役立つ知識をみんなで実践しながら学びを深めている第二藤田学区。物品だけでなく知識や体力の備えもしっかりできていると、いざという時も安心ですね!
BY のっぷ
令和4年度に特に力を入れていきたいこと
令和4年度は災害時の避難所となっている二藤小学校の体育館で、備品のパーティションテント、簡易ベッドなども利用して半日宿泊訓練を行います。また、懸案となっていた真備町の水害から学ぶ研修も実施する予定にしています。
10月実施予定の「ふじた桃太郎どんぶらこまつり」でも防災コーナーを設置するとともに、プログラムに「171災害用伝言ダイヤル」の練習も入れて災害時に活用できるよう取り組みます。
こうした訓練や研修を通じて、非常持ち出し品や備蓄品についての準備と、日頃からいつ来るかわからない災害に対して備える事の大切さを学び、各町内会や班・団体などでも実践的な訓練を行い、安全安心な二藤作りを目指したいと思っています。
関連リンク
「第二藤田学区大規模災害対策委員会」のこれまでの区づくり推進事業での活動はこちら!
