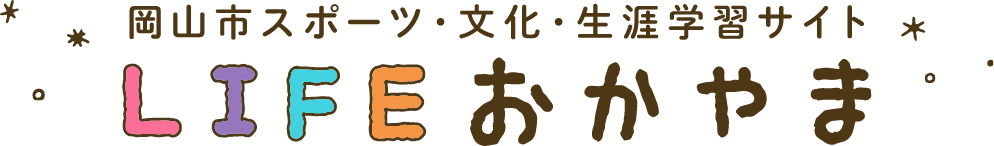
「2020 TOKYO!」
2013年9月、アルゼンチンのブエノスアイレスで行われたIOC総会で、「TOKYO」がコールされた。56年ぶりの五輪開催決定に、日本中が湧いた。
私はこの様子を自宅のテレビで見ていた。「東京に観にいきたい!」と、画面を見ながら家族と話したことが、鮮明に記憶に残っている。オリンピック・パラリンピックは世界が注目するメガイベントであり、開催国が世界に存在感をアピールするまたとない機会だ。東京のみでなく、日本中の自治体も地域活性化の契機にしようと、各自治体がオリンピック・パラリンピックに向け動き出したのを新聞等で目にしていた。
ここ岡山市でも、「ホストタウン」「事前キャンプ」といった言葉を聞くようになり、私もなんとなくそれを感じていた。
2018年。担当者として関わることに
2018年4月、人事異動により「スポーツ誘致推進室」に所属。オリンピック・パラリンピックの担当者の一人となった。
「きっと開催年度は激務だろう、東京へ観に行くのは無理か。。」という思いと、「こんなイベントに関われるのは珍しく、ありがたいこと。」という思いが浮かんだ。
同時に、2013年のあの瞬間、東京開催決定について特別な感情を持ったのは何かの縁だったのかもしれない、とも感じた。
2020年に向けた岡山市の取り組み
岡山市では、2020年に向け、着実に取り組みを進めた。その主な歩みを見てみよう。
キャンプ誘致事業
オリンピック・パラリンピックに出場する海外の選手は、日本の気候や時差に馴染むためのコンディショニングの場、いわゆる『事前キャンプ地』を求める。岡山市は事前キャンプ誘致に積極的に取り組み、2017年からの5年間で8か国10競技、延べ27件の受け入れに成功した。
キャンプでは、様々な国のトップアスリートが本市を訪れ、多くの市民と交流した。これは、キャンプ誘致の取り組みが無ければ、本市では実現しなかった光景であろう。なお、そのうち6か国8競技については、2020年本大会前の事前キャンプを実施する旨の協定締結に至った。これらは、キャンプの受け入れ主体となる競技団体の尽力により実現した成果。競技団体の皆さんは、海外選手に寄り添い、おもてなしの心で接してくれた。
ホストタウン
『ホストタウン』とは、オリンピック・パラリンピックの参加国と、スポーツをはじめ多方面で相互に交流する自治体のことを言う。本市では、国際友好交流都市の関係を活かし、ブルガリア共和国と台湾のホストタウンとなった。
具体的な取り組みとしては、ブルガリア選手や台湾選手のキャンプ受け入れのほか、中高生のホームステイの相互受け入れや、本市の市民文化交流団によるブルガリア訪問等、ホストタウンを契機に多方面での相互交流が活発化したことが挙げられる。オリンピアン等との交流事業
実際にオリンピック・パラリンピックに出場した経験のある選手と市民との交流も数多く実現した。岡山市ゆかりのオリンピアン・パラリンピアンから“生きた言葉”を受け取った子どもたちは、自分の内なる“夢”に気付き、目を輝かせていた。
オリンピックイヤー到来。パンデミックの衝撃から2020+1へ向けた動き
2020年3月24日、世界は初のオリンピック・パラリンピック延期を経験することになった。東京大会開催は暗礁に乗り上げ、世界はスポーツどころではない状況に追いやられた。
差し迫っていた聖火リレーなど、本市の取り組みもやむなく全て休止。スポーツやイベントができるということは、どれほど恵まれた状況であったのかを思い知らされたと同時に、これまでの取り組みが無に帰するかもしれない、という不安が漂った。そんな暗闇の中、大会開催の望みに向けた動き出しが始まった。インバウンドや地域活性など、当初の期待の多くは実現性を失い、様々な意見・批判が渦巻く中、アスリートが活躍する舞台を実現させる、という根本的な目的に改めて立ち返った動きでもあった。
2021年、コロナ禍での開催
コロナ対策を万全にするためのガイドラインの遵守や無観客開催など、様々な制約を受けた異例の大会開催内容が日に日に明らかになり、それに連れて業務が本格化してきた。
まずは、5月の聖火リレー。賛否両論の中、予定通り3月に聖火は福島を出発。岡山市は5月19日、夕刻に行われることになった。交通規制やオープニング式典、地元調整など、ただでさえ業務が多岐にわたる中、沿道の密集対策などのコロナ対策も求められ、全国の自治体は手探りの中、準備を進めていた。そんな最中、ウィルスの変異株による感染の波が押し寄せ、岡山市もその影響を受けることになった。公道でのリレーは取りやめ、最終到着点である岡山城下の段での無観客セレモニーのみが行われることが決まった。
今までの苦労のほとんどが無駄になってしまう結果となったが、幸いにもセレモニー開催地である岡山市に聖火はやってきた。聖火はオリンピックの象徴だ。この日のことを少しでも多くの方に伝えることが、聖火リレーに関わった者の務めであると思っている。


<写真>聖火セレモニーの様子とセレモニー参加者の集合写真
そして、いよいよ事前キャンプが近づいてきた。
コロナによる緊急事態宣言は解除され、感染の波は一旦収束したものの、世間にはまだ大会開催に懐疑的な声が多かった。他の自治体では、事前キャンプを断念する決定が次々となされ、連日、記事が飛び交った。
岡山市においても例外ではなく、事前キャンプの協定を締結していた予定の多くは、相手国からのキャンセルにより中止となった。そんな中、ドミニカ共和国の女子バレーボール、ブルガリア共和国の女子レスリングの来岡が決まった。
事前キャンプが実現
事前キャンプは、毎日のPCR検査や検温、こまめな消毒、ソーシャルディスタンスの確保など、国が示すコロナ対策を徹底し、バブル形式(外部との直接的な接触を断つ形式)のもと行われた。
残念ながら、当初思い描いていたような直接的な市民との交流は叶わなかったが、離れた客席からの観戦やオンライン形式での交流は実現した。
選手達はオリンピックの夢の舞台をベストコンディションで挑めるよう、コロナ対策で強いられた窮屈なルールを忠実に守ってくれた。
受け入れ側の岡山市のおもてなしとして、感染対策により外出ができない選手達に少しでもリラックスしてもらえるよう、宿泊ホテルの一室に、日本の夏を感じてもらえる「ミニ縁日」を用意し、浴衣を提供した。ささやかながら日本文化に触れ、リラックスできる機会になったことが、選手たちの笑顔を見て感じることができた。
そして、選手たちはもちろん、関わるスタッフも毎日PCR検査を実施し、一人の陽性者も出すことなく、無事に選手たちを東京に送り出すことができた。
オリンピックでは、ブルガリアの女子レスリング2選手が銅メダルを獲得、ドミニカの女子バレーボールチームは決勝トーナメントへ進出し、8位入賞と、素晴らしい結果を残してくれた。
各競技団体や地元岡山のトップチーム、宿泊ホテルや練習施設の方々など、多くの方々の協力無しにはこの成果は得られなかっただろう。これだけの人々を動かしたのは、オリンピック・パラリンピックが持つ大きな魅力に他ならない。


<写真>ブルガリア共和国女子レスリングチームとドミニカ共和国女子バレーボールチーム
さいごに
パラリンピックでは、パラリンピックのルーツであるイギリスのストーク・マンデビル及び全国各地で採火した火が東京に集火され、東京2020パラリンピック聖火として東京のまちを駆け抜けた。
このパラリンピック聖火となる‟岡山市の火“を吉備津神社から採火し、岡山市としてのオリンピック・パラリンピックに向けた取り組みは一通り終了した。現在は、小中学生を対象とした交流事業により、スポーツを通した学びの機会を提供している。
オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みは、まさに国民的イベントにふさわしい、特別なものであった。
アスリートが真摯にスポーツに打ち込む姿は、国民に感動や元気をもたらし、「スポーツの価値」を再認識させてくれた。その認識は、コロナ禍の中開催されたことにより、よりクローズアップされたと思う。
オリンピック・パラリンピックを通して得た経験やノウハウは、決して一過性のものにしてはいけない。改めて認識されたスポーツの価値とともに、オリンピック・パラリンピックのレガシーとして引き継ぎ、市のスポーツ振興や地域活性に繋げていくことが、オリンピック・パラリンピックに関わった者の今後のミッションだと感じている。

執筆者
岡山市スポーツ振興課 スポーツ誘致推進室 室長 後藤 浩志