 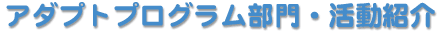
  竜之口くるまづか公園愛護委員会 竜之口くるまづか公園愛護委員会
岡山市四御神
竜之口くるまづか公園訪問記
岡山市初のワークショップによる公園
竜之口くるまづか公園という少しいかめしい名前の公園ですが訪ねてみると、こざっぱりとして落ち着いた公園でした。ウォーキングする人にはお馴染みの龍ノ口山の登り口にあります。車塚はこの公園のすぐ西側の山の頂上にある古墳の名前です。
 この公園は、市の公園でワークショップによりできた最初の公園です。「ワークショップ」とは、利用者や関心のある人たちの意見を、より多く取り入れて行う街づくりのことです。 この公園は、市の公園でワークショップによりできた最初の公園です。「ワークショップ」とは、利用者や関心のある人たちの意見を、より多く取り入れて行う街づくりのことです。
平成8年、会長の山田さん達は竜之口学区の子どもの遊び場マップを作っていました。遊び場を調査するうち、遊園地はあるけど大きな公園はないこと、また中学生や高校生が利用するような公園もないことに気づきました。
そんな中、平成10〜12年にかけて、四御神の公園をワークショップ方式でリニューアルすることになりました。子どもから大人まで幅広い年齢層の地元の人たちが集まり、この公園をどんな公園にしたいか話し合い、模型を作ったり予算配分を考えたりしてみんなで公園の計画をたてました。「バスケットのゴールが欲しい」「小さい子どもを連れてきたとき休むあずまやがあったらいいな」「中高生にも魅力ある公園にしたい」などいろんな意見を出し合いながら今の公園が生まれました。
公園が完成した後、このワークショップに参加したメンバーが中心になり愛護委員会を結成しました。季節ごとの花を植えたり清掃したり、購入した草刈機で公園の周囲の草を刈ったりもしています。
 
訪ねた日は花の植え替えの日でした。市の緑化推進課からの花の苗が運ばれてきました。夏を彩った花が抜かれ、土の養生もしてナデシコなどの3種類の花が次々に植えられていきます。「公園で体を動かして作業するのは楽しくて、リフレッシュする。その楽しさを味わって欲しい」と山田さんは言います。
 現在は、バスケットコートを利用する中学生や高校生も多いそうです。ただ、この公園は団地の奥まった位置にあるため、学区の人でもこんな公園があるのを知らない人がたくさんいます。山田さんは、竜之口小学校の児童たちの「地域の公共施設調べ」で、公園のできたいきさつを話しに行ったこともあるそうです。 現在は、バスケットコートを利用する中学生や高校生も多いそうです。ただ、この公園は団地の奥まった位置にあるため、学区の人でもこんな公園があるのを知らない人がたくさんいます。山田さんは、竜之口小学校の児童たちの「地域の公共施設調べ」で、公園のできたいきさつを話しに行ったこともあるそうです。
そしてもっと多くの人にこの公園を知って欲しいので、今後も小学校とどう繋がっていくかを模索中で、鳥やトンボなどの自然観察会を開くことも検討中です。この公園の上空は渡り鳥の渡りのコースなのだそうです。
ワ―クショップに参加すること、公園の管理に参加することなどを通し、人と人との繋がりが広がって、一人一人の思いが少しずつ実現していくのだろうと思いました。
  国富瓶井町
長寿会 国富瓶井町
長寿会
岡山市国富
蝋梅(ロウバイ)の里づくりを目指す!
 静かな たたずまいの中で 静かな たたずまいの中で
 私が取材に行った日は、久しぶりに抜けるような青空の小春日和でした。それで散策も楽しもうと少し遠いところから歩いて、野菜畑もあるような道をあっちへ曲がったりこっちへ折れたりしてみました。 私が取材に行った日は、久しぶりに抜けるような青空の小春日和でした。それで散策も楽しもうと少し遠いところから歩いて、野菜畑もあるような道をあっちへ曲がったりこっちへ折れたりしてみました。
すぐそばの国道の騒音が嘘のように消えて、全く別の街へ来たような感じです。近くの山では小鳥たちが高い声で鳴き交わし、どの家も静かで、よく手入れされた庭には秋の花がきれいでした。
沢ガニでもいそうなきれいな砂の小川のそばのみちを上っていくと、通称「赤門」と呼ばれている仁王門が、にゅう!と現れてきました。安住院の建物も朝の光の中で仏様のように静かな佇まいを見せていました。
  活動を始めて8年 活動を始めて8年

町内会長
菊山稔英さん |
瓶井町長寿会は「蝋梅の里づくり」を目指して活動されていると聞いてきましたが、まさにこの街の雰囲気は蝋梅の花と香りにぴったりだと、取材の前に納得してしまいました。
安住院の駐車場脇のお庭を拝見していると、長寿会の方らしき人達が次々に集まって来られました。さっそく菊山稔英町内会長さんにお話しを聞いてみますと、
「町内の60歳以上の方なら誰でも参加できるが強制はしないというのが決まり」とのことでした。
この活動を始めて既に8年経ったそうで、大きく生長した木も、一年生の木もありました。
  ロウバイの魅力と育成 ロウバイの魅力と育成

園芸部長
逸見富洋さん |
蝋梅の実はウメの実とは似ても似つかぬもので、実が枯れてくると網のような袋になり、南京豆を小さくしたような種が5つほど中に入っています。
ここでは、実生といって種から苗づくりをしています。
蝋梅を選ばれたきっかけは、園芸部長の逸見富洋さんが、もう長く栽培されていて、蝋梅の花の美しさと香りの上品さに目を付けられ町内で増やしていくことを提案されて賛同が得られたとのことで、菊山会長さんは「町内全体の運動にしたい。町内各戸に種や苗を配ってこの町を蝋梅の里にしたい。そして自分たちだけが楽しむのではなく、多くの人にもぜひ見てもらいたい」と意気込みを話されました。
 1月中旬から下旬が見頃 1月中旬から下旬が見頃
参加された皆さんは世間話をしながらもテキパキと作業され、あっという間に散会されました。30分ほどでやめるのが長続きのコツだということです。
愛知県の東海テレビが「蝋梅の里」と全国に紹介したこともあるようです。見頃の1月中〜下旬には皆さんも是非おでかけください。(市民環境記者 広坂)
 
| ロウバイ〈蝋梅〉ロウバイ科: 日本には江戸時代初期に渡来し、観賞用によく植えられている。1〜2月、葉がでる前に香りのよい黄色の花を開く |
|




