県指定重要文化財金山寺三重塔は、天明8年(1788江戸時代中頃)に建てられている。平成11年から行っている修理事業の一環として、建物の基礎構造の調査を行った。
その結果、金山寺三重塔の基壇は
(1) 山を削りだして平坦地を造る
(2) およそ縁石の範囲(7〜8m四方)にあたる部分を1段深く掘り下げる
(3) 根石(推定90×140×90cm)を置く
(4) 根石の上部付近まで土を盛る
(5) 根石の上に礎石(約50×50×60cm)を立てて置く
(6) 礎石の上部が数cm見える程度まで亀複状に土を盛る
(7) 最後に縁石を並べる
以上のような行程が復元できる。盛土はそれほど強く叩きしめたものではないが、堅い層と柔らかい層を交互に積んでおり、版築(はんちく)を意識していたと思われる。また、盛土の中から石加工時にできた石屑が出土したことから、礎石や縁石の加工も基礎工事と並行して行われたようである。
今回の調査は小面積ではあるが、現存建造物の地下調査に制約がある中、近世寺社建築の基礎構造の解明に大きな手がかりを得られたと考えられる。
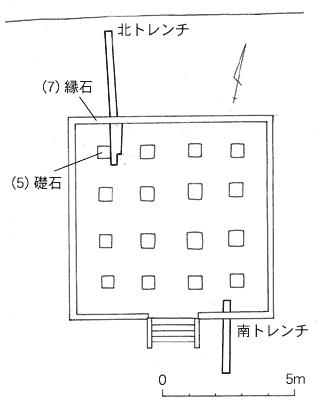 金山寺三重塔トレンチ位置図 |
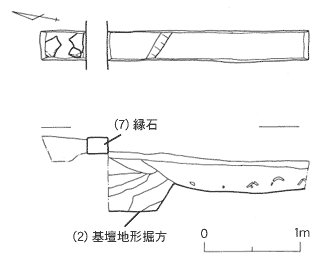 南トレンチ平面・断面図 |
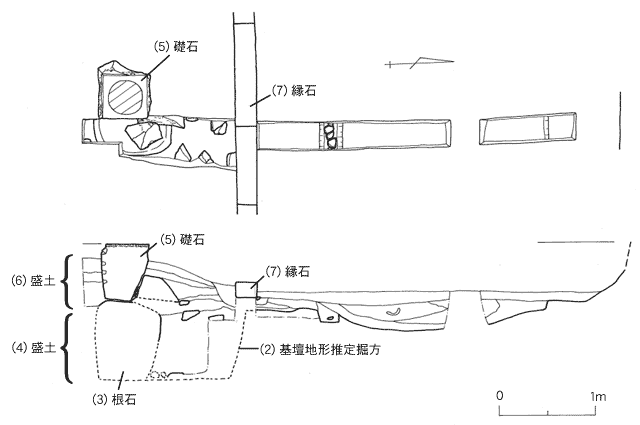 北トレンチ平面・断面図 |
|
 (5)礎石を斜め方向から撮影 |
|