 |
| 本堂 |
岡山市国富にあり、瓶井山禅光寺安住院と称する。寺伝によると、天平勝宝元年(749)に報恩大師によって建立された備前四十八ヶ寺の一つとして創建されたという。江戸時代の寺領は八十石である。当寺は後楽園の借景として有名な多宝塔のある寺として一般に知られている。
 本堂(市指定重要文化財) 本堂(市指定重要文化財)
棟札により、慶長六年(1601)十二月十八日に新造されたことがわかる。建築場所は現在地よりも南方数百mの位置で、境内の塔頭寺院等の関係で寛政十二年(1800)年に現在地に移築された。そのため、当初は正面五間、側面六間の平面で、建物の四面に切目縁を廻らし、軒は四面とも垂木幅と同じ幅間隔で並べた本繁垂木が二重であったが、移築後、切目縁は正面と両側面の三面となり、軒は背面の本繁垂木が一重に改築された。しかし、中世における密教本堂の形式をよく残している。入母屋造で本瓦葺である。
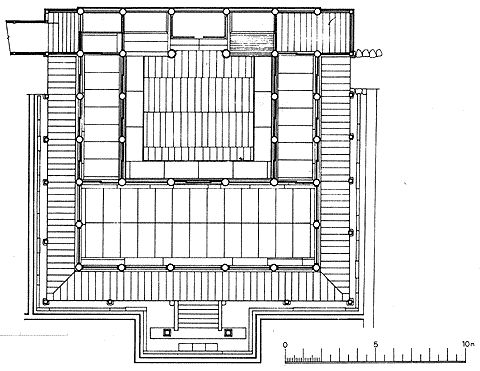 |
| 本堂(参考文献より引用) |
 多宝塔(県指定重要文化財) 多宝塔(県指定重要文化財)
 |
| 多宝塔 |
棟札によって寛延四年(1751)の建立が明らかである。元禄七年(1694)に岡山藩主池田綱政に再建を許されたが、実際の建築は次の継政の代といえる。本瓦葺、三間二重の多宝塔で、四面の各中央の間に置いた蟇股の彫刻は四神を題材にしている。内部は内陣と外陣に分け、内陣の須弥壇に大日如来と脇立の不動明王、降三世明王を安置する。この多宝塔は児島由加山の多宝塔につぐ県下二番目の規模を有する。
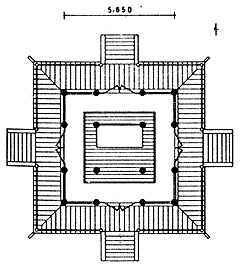 |
| 多宝塔(参考文献より引用) |
 仁王門(県指定重要文化財) 仁王門(県指定重要文化財)
 |
|
仁王門 |
当寺院内最古の現存建物である。康世二年(1456)の建立を示す仁王堂造営の奉加控帳があるが、後世の修理が目立つ。延宝四年(1676)の棟札に伴う修理によって新造に近い大改造を受けたと思われる。三間一戸の楼門で、屋根は入母屋造、本瓦葺、大棟の両端に瓦製の鯱を立てる。中の間を通路とし、両脇の間に金剛垣を設けて金剛神二神を安置している。
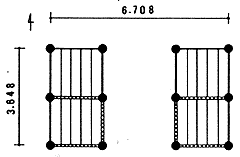 |
| 仁王門(参考文献より引用) |
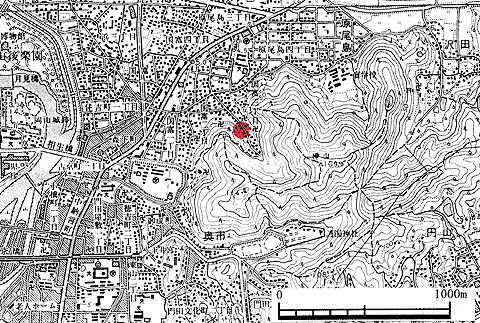 |
| 位置 |
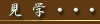 |
岡電バス・宇野バス「国富」下車、徒歩15分 |
|
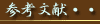 |
巌津政右衛門『岡山の建築』日本文教出版株式会社 1967年
岡山県教育委員会『岡山県の近世社寺建築』 1978年
岡山市教育委員会『岡山市指定重要文化財安住院本堂保存修理報告書』 1993年 |
|

