
| 本段御殿は、藩主の私邸で、日常生活の場である。そのため、本段御殿へは一般の藩士の出入りは厳しく禁止されており、本段と表向を隔てる不明門は常時閉鎖されていた。そこで御殿への出入りは、藩主は渡り廊下を、御殿勤めの下働きの者は六十一雁木を使用していた。御殿は南端に玄関、ついで台所が設けられ、その奥に藩主の部屋と女中の部屋が、そして最も奥に側室の部屋があった。天守閣2階には藩主の部屋である「城主の間」が設けられていたが、江戸時代を通じて使用されることはなかったという。 |
|
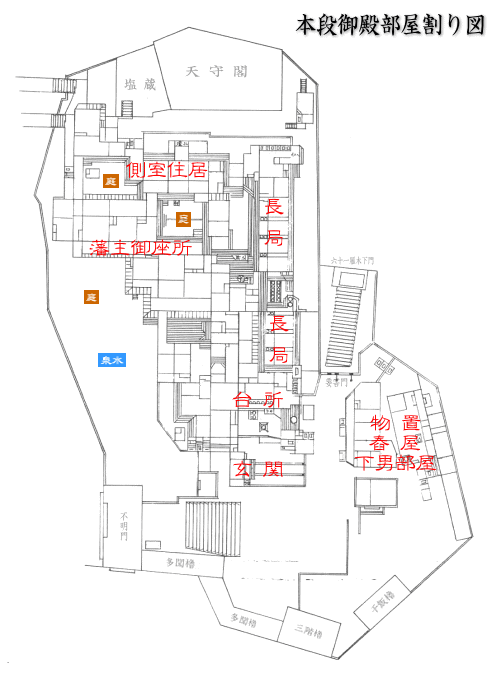 |
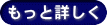 |
| |
| 各殿舎の解説 |
| 側室住居 |
| 藩主の正室は江戸屋敷住まいのため、岡山城に部屋はない。 |
| 藩主御座所 |
| 「御」の文字の真下の部屋が御座所の中でも中心となる「長春の間」で、縁側を隔てて庭園を望むことができた。 |
| 長 局 |
| 御殿に勤める女中の部屋。各部屋6畳3畳に押入れ付きで、北に隣接して共同風呂と便所が設けられていた。 |
| 台 所 |
| 20室以上からなる広大なもので、隣接して西には中居や留守居など御殿勤め者の部屋があった。 |
|
|
|
