アユモドキってどんな生きもの?
アユモドキは、京都府亀岡市と岡山県にだけ生息する珍しい淡水魚で、1977年(昭和52年)より国の天然記念物に指定されています。大きさは15から20センチで、にょろりと伸びた口ひげと体のしましま模様が特徴です。
アユモドキは田んぼ、用水路、川など人間の暮らしととても身近な環境に生息しています。しかし、近年、アユモドキが産卵できるような環境が減少していることなどが原因で、その数は年々減ってきています。アユモドキが減ることは、多様な生きものだけでなく私たち人間が暮らす環境もいずれ影響を受ける可能性があります。アユモドキ
千種小学校で行われているアユモドキの保全活動
千種小学校で行われているアユモドキに関する授業の様子
学校データ
- 学校名:千種小学校
- 住所:岡山市東区瀬戸町鍛冶屋391 [地図]
- 問い合わせ先:086-953-0604
- ウェブサイト:岡山市立千種小学校別ウィンドウで開く
2010年(平成22年)から、瀬戸地区にある千種小学校では、アユモドキをふやすため研究者と一緒にアユモドキの人工繁殖が行われています。
アユモドキの人工繁殖に取り組むのは、5年生の子どもたち。
人工繁殖を行うまでに、授業を通じてアユモドキの生態について学んだり、アユモドキの生息する環境について学んだりしています。
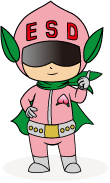
僕も授業に参加して、子どもたちと一緒に川を調査したよ!
水辺の学習
水に入ったとたん、子どもたちからあがる「気持ちいい~!」、「魚がたくさん泳いでる!」などの声。
水の冷たさや川の中を泳ぐ淡水魚の姿に、子どもたちは大はしゃぎでした。※それから岡山市の職員や岡山淡水魚研究会の方の説明を受けて、網をつかって淡水魚を捕まえていきました。
※アユモドキの飼育・捕獲は法律で禁止されています。この授業では、特別に許可を得て行われました。
子どもたちに魚の捕まえ方について指導している様子
夢中になって魚をとる子どもたち
身近な水辺で暮らすアユモドキ
約一時間でつかまえた淡水魚は、全部で約30種類!その中でアユモドキはたったの2匹でした。
子どもたちは、「どうしてアユモドキはこんなに少ないのか?」などの小さな疑問からアユモドキへの理解を深めたり、他にどんな淡水魚が生息しているか説明を受けて、身近な水辺の環境やその生態系について学んだりしました。身近な環境で生息する魚に興味深々な子どもたち
子どもたちが描いたアユモドキの絵
アユモドキについて理解を深めた子どもたちは、水辺の学校から約一ヶ月後に人工繁殖を行いました。現在、人工繁殖で生まれたアユモドキは小学校で飼育されています。
5年生だけでなく、他の学年の子どもたちにもアユモドキは身近な存在として親しまれています。また、壁新聞を作ってアユモドキの生態や、アユモドキが生息できるような環境を守る大切さについて保護者や地域の方に伝えています。アユモドキが生息している水路など身近な水辺の環境を守ることが、多様な生きものや人間がこれからも安心して暮らせる環境を守ることにもつながっていく。そのことについて子どもたちは授業を通じて学んでいます。
そして、「アユモドキを未来へ残していくために、どのように行動すればいいか?」など自ら考える力が子どもたちの中で育まれていきます。

人工繁殖で使用するための水槽を準備している様子
人工繁殖を行っている様子
千種小学校で行われているアユモドキの保全活動には、いろんな方の協力が欠かせません。
地域の方が、アユモドキのえさとなるプランクトンの入っている田んぼの水を、毎日くみあげて学校に届けたり、岡山市の職員や淡水魚研究会の方々がアユモドキの詳しい生態について指導しています。学校だけでなく、色んな立場の方が連携することで、アユモドキや自然環境を守る活動が行われています。
岡山市教育委員会文化財課 岡本芳明さんにお話をきいてみたよ!
「現在はアユモドキの数を増やすために人工繁殖を行っていますが、将来的にはアユモドキやいろんな生きものが生息しやすいきれいな水辺の環境を整備したり、子どもたちが自然の中で遊べる環境を地域ぐるみでつくっていきたいですね。
子どもたちが大人になってからも、アユモドキが生息できる環境を保全し次世代に豊かな未来をひきついでいく。そんな地域になっていってほしいですね。」
身近な自然環境は私たちの暮らしと関係していて、その環境や生きものを守ることにもつながっているの!この考えはESDをすすめる中でとても大切なことなのよ!
