「特定非営利活動法人co2sos」とは?
2008年に発足した「特定非営利活動法人co2sos」は、国内外で測定された二酸化炭素濃度の公開や科学体験教室などを行い、地球温暖化問題の解決を目的に活動する団体です。
2017年4月から環境学習事業の一環として、仮想の3D空間で宇宙や古代の世界を体験できる全10回のイベント「バーチャル科学館を体験しよう!」を開催。大学生スタッフが主体となって行うこの活動が「ESD岡山アワード2018」にて「奨励賞」を受賞しました。
今回は、岡山市にある「人と科学の未来館サイピア」で行われた同イベントに焦点を当て、子どもたちが楽しみながら環境や科学について学べる取組を紹介します。
バーチャル科学館とは?
バーチャル科学館とは、仮想3D空間に作られた科学館で、海洋探査や宇宙開発などの様々なコンテンツをバーチャル体験できるシステムのことです。
参加者は「アバター」と呼ばれる自分の分身を仮想3D空間で操作し、遠隔地にいる講師は参加者と同じ画面を共有しながら、インターネットの音声通話により、そこに登場する海洋生物や恐竜の生態などについて解説します。

2018年5月に開催された講座の様子
イベント開始のきっかけは、co2sosのスタッフが、仮想3D空間を通じて知り合った海洋研究開発機構の西村さんとサイピアで講義を実施し、好評を博したこと。
最先端のデジタル技術を使って、現実世界ではありえない位置や角度から世界を見学・体感し、楽しみながら地球温暖化などの環境問題について関心を深めることができます。
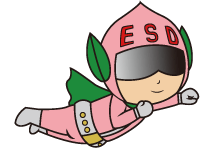
2018年11月17日(土曜日)、バーチャル科学館を見学させてもらったよ!
操作体験で宇宙や恐竜の世界を探検!
この日参加していた男の子2人は、国際宇宙ステーションや海洋世界のコンテンツを操作体験中。大学生スタッフに操作方法を教えてもらいながら自由にアバターを動かします。
ロケット内部に潜入したり、魚の背に乗ってサンゴ礁を探検したりと、目の前に広がるリアルな仮想3D空間にすっかり夢中の様子です。

アバター操作体験

大学生が操作説明
案内役を務めるのは、遠隔地にいるバーチャル科学館の講師であるヤンさん(前出の海洋研究開発機構・西村さん)とアカーシャさん。会場では大学生スタッフの賈さんが司会を務めます。
次に案内してくれたのは、恐竜が生息していたジュラ紀の世界。早速目の前に大きな恐竜が現れました。
「ヤンさん、これはどんな恐竜ですか?」
「何を食べますか?」
気になることはすぐに質問。専門知識が豊富なヤンさんが丁寧に答えてくださるので、短時間で恐竜についての知識がぐんと広がりました。
イベントのスタッフ、協力体制
今回のスタッフは、バーチャル科学館の外部協力者2名と大学生3名、そしてco2sosのボランティアスタッフの計6名。
イベントは大学生が主体となって企画から運営まで行います。運営メンバーである田辺さん、李さん、賈さんにお話を伺いました。

会場でイベント運営を行う大学生3名
田辺さん(左)・李さん(中央)・賈さん(右)
田辺さん
来てくれた子どもたちのサポートをしています。途中で飽きてしまう子や、まだ理解ができない子にクイズを出したり、一緒に塗り絵をしたりします。こうした工夫で、少しでも楽しく、興味を持ってもらえる時間にできたらいいなと思います。
李さん
岡山大学で情報工学を学び、今は大学院でAR(拡張現実)ナビの開発・研究をしています。操作マニュアルの作成やバーチャルアプリの開発など、イベント開催するにあたっての準備が大変でしたが、子どもたちが喜んでくれたのがうれしく、毎回やりがいを感じています。
賈さん
中学・高校・大学と放送部だった経験を生かし、操作体験の司会を担当しています。最初はヤンさんが説明するタイミングに合わせられず苦労しました。ヤンさんの説明をうまくかみ砕いて、子どもたちに分かりやすく伝えるよう心がけています。科学館の窓口役ながら、子どもの興味をひいたり話を引き出したりしていると、保育士さんのような役割もあるなと感じます。
イベントでは、VRゴーグルにスマホを装着して行うVR体験や、小学校低学年向けの環境クイズも用意。これも大学生スタッフの発案だそうです。

VR体験を楽しむ小学生

小学生向けのクイズやぬり絵とVRゴーグル
おわりに
「子どもたちが楽しみながら環境や科学について学ぶことで、ESDにつながる発想や興味を持ってくれるとうれしいです。大学生スタッフには、運営を通して自分の知識や技術を生かしてもらい、将来的なESD活動の担い手として活躍してくれることを期待しています」と語るのはco2sosボランティアスタッフの朝原さん。
今後もイベントのさらなる発展を目指しています。

楽しく環境学習ができて、未来のESD活動につながる素晴らしい取り組みだね!
