My Dream Project(MDP)/みまさか学
学校データ
- 団体名:岡山県立林野高等学校
- 住所:岡山県美作市三倉田58-1[地図]
- 問い合わせ先:0868-72-0030
- ウェブサイト:岡山県立林野高等学校別ウィンドウで開く
美作市に1908年(明治41年)に創立された岡山県立林野高等学校は、今年創立113周年を迎えた伝統校です。同校では、総合的な探究の時間「MDP」と、学校設定教科(選択教科)「みまさか学」という独自の学習を行っています。
My Dream Project(MDP)は、地域をフィールドに探究活動を行ったり、発表したりする「総合的な探究の時間」のこと。課題解決力やコミュニケーション能力など、社会人として必要な能力の育成を目的として、1年生から3年生の縦割りグループにより課題探究を行っています。また、2、3年生を対象とした独自の学校設定教科「みまさか学」は、地域をフィールドとした体験型活動や、様々なビジョンを持った人々との出会いを通して、地域への理解を深め、課題解決能力を育成することを目標とした学習の時間です。
今回は、1、2年生全員で4月から取り組んできたMDPの「中間報告会」を取材しました。
My Dream Project(MDP)中間報告会
林野高校ではSDGsの17の目標のうち15(11番、17番以外)の目標を「国際」「教育」「社会」「自然」「健康」の5グループに分け、1年生から3年生が縦割りで課題探究を行っています。さまざまな分野の地域の達人に話を聞いたり、地域に出かけて実際に調査をしたりする「デアイ場」や、グループ活動のまとめである「実践報告会」などをおもな活動内容とし、年間を通じて探究を深めていきます。
11月9日(火曜日)に行われた「MDP中間報告会」では、全17グループが前・後半に分かれて3回ずつ発表を行い、1、2年生209人が各教室で発表を聞きました。教育グループの「教育格差について」や、社会グループによる「ずっと住みたいと思えるような地域づくり」、国際グループの「伝統文化の後継者不足」など、地域の人々へのアンケートや「デアイ場」で聞いた生の声を通じて各グループが見出した地域の課題について発表されました。また、活動の結果わかったことをどのように解決していくか、今後の展望についても報告がありました。

スライドを使った発表の様子
今回の報告会では、これまでの取り組みをわかりやすく発表できるかどうか、また他者の発表を聞いて、今後の探究に向けた助言をすることができるかどうかの2つが目標です。そこで、2人ずつの発表者は、グループで作成した資料(スライド)をChromeキャストまたは有線を使ってプロジェクターに投影しながら、内容が伝わるように声量や話すスピードなども考えながら発表。終了後は、質疑応答をし、Chromebookを利用して、発表の良かった点や改善した方が良い点をフィードバックします。発表は3分、質疑は2分、フィードバックと移動が5分という制限時間にも気を付けなければいけません。
発表を聞いていた1年生男子は、「入学したころは、先輩たちの取り組みを見ているだけの立場でしたが、自分の意見を発信するようになって、前より達成感があります」。また2年生女子は、「2年生になって主体的にMDPに取り組むうちに、自分の目標や夢に前向きになりました」と感想を答えてくれました。
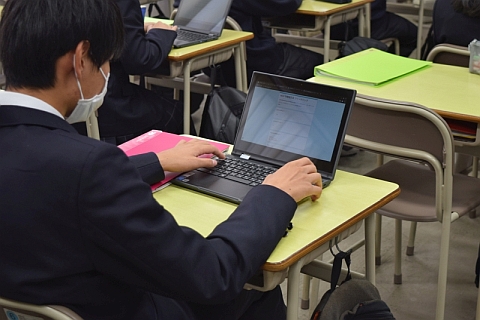
発表を聞いた生徒はアンケートフォームからフィードバックを送信
後半は、教室を移動し、教育グループの「ICTの自主的な活用方法を探究する」、自然グループの「洪水被害を防ぐためにはどうすればいいのか」、健康グループの「栄養によるスポーツ力の向上」など幅広いテーマについての発表を見学しました。

コモンホールでの発表
「教育グループ ICT活用チーム」は「ICTの自主的な活用方法を探究する」をテーマに、課題のオンライン提出や、部活OJT、勉強を互いにオンラインでサポートする「教え合い」などの取り組みを行いました。なかには利用者が集まらず失敗する取り組みもあったそうです。しかし、今年は無観客開催になってしまった体育祭「あがりん祭」の様子を家庭に届けるために行ったオンライン中継やSNSへの写真投稿の取り組みは、いずれも多くの人が閲覧し、成功に終わりました。オンライン中継の実践は「デアイ場」での日立工業専修学校(日専校)との交流が参考になったのだとか。他校との交流によって、ICTを活用するメリット・デメリットについての意見を共有できたという成果があった一方で、反省点は学校全体を巻き込めなかったこと、今後は学校の垣根を越えて、より多くの学校とも交流していきたい、と発表を結びました。

質疑応答の様子
「MDP」担当の三宅杏奈先生
本校の「MDP」活動の特徴は、全学年縦割りグループで学ぶことと、SDGsの目標からテーマを決めていることです。取り組みにより、地域の課題や魅力に気づくきっかけになり、自分の意見を伝える練習にもなっています。残る半年で地域の課題に対して「自分たちに何ができるか」をアウトプットし、2月に総まとめの発表を行います。1年間の成果を通して、ひとり一人が表現力や思考力を身に着けて成長してくれることを願っています。
みまさか学
地域課題が山積する中山間地域である美作地域そのものを教材とし、「みまさか学」という教科名が指し示すように、その地域固有の課題を見出してその解決策を提案・実行することを目指すのが、2、3年生の選択教科である「みまさか学」です。
「MDP中間報告会」で「教育グループ ICT活用チーム」として発表を行った長畑結さん(2年生)も、「みまさか学」の選択者のひとり。長畑さんが「みまさか学」から学んだことや、その成果についてお話をお聞きしました。
中学の頃から発表や探究活動が好きだったので、2年生で選択しました。今ある地域の魅力をリメイクして新たに発信することをテーマに4人で活動しています。消費者と生産者をつなぐことで、何か経済活動につながる取り組みになればと思っています。「みまさか学」を通じて、自分の考えていることを伝えたり文章化したりする力が身につきましたし、知らなかった美作の魅力を再発見できました。将来は学校教員志望ですが、「地域学」の活動にもずっと携わっていきたいです。

「みまさか学」担当の芦田正徳先生
地域の方の支援を受け、美作地域そのものを教材として探究を深める本校独自の選択科目です。今年はコロナ禍で地域の人たちとのコミュニケーションを深めていくための活動がしづらい状況でしたが、生徒は工夫しながら頑張って取り組んでくれています。「MDP」や「みまさか学」で培った探究心やプレゼン力を進学に生かし、実際に地元の教員として活躍している卒業生もいます。「みまさか学」での学びをきっかけに視野が広がり、自分の将来の生活や人生に関わるような活動になればと期待しています。
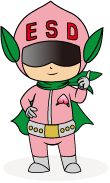
どの生徒も真剣に取り組み、発表していたよ!集大成の発表に向けてがんばってね!
ご注意ください
- このページでは、施設、企業、団体、NPO等をご紹介しています。
- 企業、団体、NPO等の商品・サービス、活動内容等及びその他リンク先のウェブサイトの内容等についての責任は、各企業、団体、NPO等に帰属します。また、岡山市及び本ウェブサイトの管理・運営者が、特定の商品・サービスや企業、団体、NPO等を推奨等するものではありません。
- お問い合わせ・ご質問などは、各企業、団体、NPO等のお問い合わせ先にお願いします。
- 免責事項をご確認のうえ、情報の利用はご自身の判断で行ってください。
