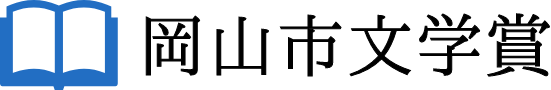三本の柿の木
ぼくの家の前には川が流れております。はば二メートルぐらい。しかしいつでも水があふれるように流れていて、底にはえた藻が長くのびて、ユラユラゆれております。ハヤやフナはその藻の中にたくさん住んでおります。きっとそこに、魚の村や魚の家があるのでしょう。
ぼくの家ではその川へ石段がつくってあって、そこでなべやかまを洗います。せんたくものもいたします。朝おきて、ぼくが顔も洗います。おばあさんやお母さんがたんぼからかえって来て、くわも洗えば、足も洗います。牛もそこへおいこんで、前にはお父さんが足やからだを洗ってやりました。そんなにいろんなものを洗いますけれども、流れが早いもので、洗いものはどんどん川しもへ流れて行って、水はいつもきれいにすんでおります。
その川岸には春はきつね花が咲き、秋は野ぎくが咲きます。そのきつね花や野ぎくによくヤンマが来てとまります。ぼくはよくそのヤンマをとります。ところで、そうだ、そこでホタルをとることもあれば、ハヤやフナを釣ることもあります。しかしぼくが一ばんたのしみなのは、秋のおわりごろ、柿のはがちって、そのみだけがきいろく赤く枝にのこっている、そこをかにがさがって来ることでした。目の荒い大きなあみをそこに受ければ、一晩に五十も六十もかにがとれるのです。それをにて食べれば、―そう、おじいさんもお父さんもこれが好きで、舌をならして食べられたそうです。早く秋になればいい。
だって、秋になれば、柿の木にそれこそ柿の実が枝が折れそうになるほどなるのです。そんな柿の木がぼくの家には三本もあるのです。それがずっと一列に川岸へ並んでおります。一番左がわのがおじいさんの平作柿、その次がお父さんの平太柿、次がぼくの泉吉柿です。おじいさんの柿の木はもうとしをとっていて、木の大きいわりに実がなりません。おばあさんがひりょうをやったり、人をたのんでむだな枝を折ったり、大切にせられますけれども、それでも去年ぼくがかぞえてみたら、二百くらいしかなっておりませんでした。それにくらべて、お父さんの柿の木は、五百も六百もなっていて、何度かぞえても、ぼくにはせいかくにかぞえられませんでした。ぼくの木はまだ小さくて、三十六しかなっていなかった。
だけども、どうしてそれらの柿の木を、おじいさんの木だの、お父さんの木だのというか、知っていますか。むずかしいわけはありません。おじいさんが生れた時、おじいさんのお父さんが―その人は甚七さんといったそうです―その甚七じいさんが、おじいさんのためにといって、どこか山の方から柿の苗を一本買ってきてそこへ植えられたそうです。それがおじいさんの柿の木です。何年昔のことでしょう。おじいさんが生きておられれば、七十近くになられるというのですから、やっぱり七十年も昔のことでありましょう。
お父さんの柿の木も、やはりお父さんが生れた時、おじいさんが―この人は平作さんといいました。―その平作じいさんがお父さんのためといって、これも山の方から買ってきて、その苗を植えたのです。これがお父さんの柿で、四十五年くらいになるそうです。ぼくの柿の木も同じで、これは十二年にしかなりません。でも、ぼくがお父さんになったらきっと何百という大きな柿がなるにちがいありません。そしてぼくのような子どもが生れて来て、うまいうまいと、いくつも、いくつもたべるでしょう。
うん、そのうまいことからいえば、おじいさんの平作柿が家では一番うまいのです。大きさも一番大きいのです。でも初めのうちはしぶくて食べられません。しかし秋のおわりごろになるとくらべるもののないほどおいしくなり、ぼくが一番たのしみの柿の木です。でも、枝々に赤々といつまでものこっていて、夕日のさす時など遠くのたんぼからでもとても目立って見えるものですから、からすや子どもが集って来て、つっついたり、とって行ったりするのです。ぼくが腹をたてて、からすに石を投げたり、子どもを追いかけて行ったりしますと、おばあさんはかえってぼくをしかり、
「センや、そんな手荒なことをするものではない。」といいきかされます。ぼくは泉吉というのです。
「だって、うちの柿じゃないか。」
ぼくがいいますと、
「うちの柿といっても、あれはおじいさんの柿の木です。お前もおじいさんからいただいているのじゃ。だからからすであろうと、よその子どもであろうと、ほしいものにはやらなけりゃ。きっとおじいさんも喜んでおられるよ、世の中のことって、何でもひとりじめにするものではない。」
おばあさんはいわれるのでした。
「そうですか、そうですか。ナムアミダブツ。」
いつものことですから、ぼくがふざけていいますと、
「そうとも、そうとも、ナムアミダ、ナムアミダ。」
おばあさんがにこにこしていわれます。
ところで、ぼく下手なことして、話の書き方をまちがえました。だから、ここで、話を初から書きなおします。
おばあさんに聞いた話ですが、平作おじいさんの生れたのは明治十二三年頃だそうです。で、男の子が生れたというので、そのお父さんの甚七さんはひじょうに喜び、生れてまだ五日もたたないのに、もう山の方へ行って、その村一番という大きくておいしい柿の苗をもらってきてくれました。それはほんとに小さくて、―というのはつぎ木をしたばかりで、先に弱々しい若葉が二三枚、心ぼそげに風にふるえていたそうです。それを川ばたの、ぼくんちのやしきに植えると、甚七さんははさみをもってきて、その木のそばでかちかちとならしました。
「早く大きくなれ、ならんと、はさみでつみ切るぞ。」
それはそういういみなんです。だってさるかに合戦のお話にちゃんとそう書いてあります。だから柿の木を植えた場合、ぼくんちの村では昔からみんなはさみの音をたてて、柿が一時も早く大きくなるようおどかすことになっているのです。
で、そのせいかどうか知りませんが、その柿は風に吹かれたり、雨にたたかれたり、霜にふられたり、雪にうずめられたりしましたが、それでも少しも弱りもせず、ずんずん大きくなりました。甚七じいさんが、風の日にはそえ木をしたり、さむい冬にはかんぴというのをやったりしておられたそうですが、平作さんが三つの時には、初なりの柿が十も枝についたそうです。甚七じいさんは大喜びして、それが赤くじゅくしたのをまち、ある日のこと赤いごはんをたいて、その柿二つずつと一しょにきんじょの家に配りました。じゅう箱の上に、
「吾子三つ、柿も十ほどなりにけり。」
と書いた紙がのせてありました。それは発句というのだそうです。
平作さんが五つの頃だったそうです。柿の木は大分大きくなり、年々三十も五十もなるようになっていました。甚七さんはある日さるかに合戦の話を平作にしてやりました。そしてその柿の木をむかしかにが来て種をまいた柿の木だと話しました。ところが、その明くる日です。雨あがりの秋の日だったそうですが、ほんとうに大きなかにが一匹、その木のねもとにやって来て、そろりそろりと歩いていました。これを見ると、平作さんはおどろいて顔色をかえました。すぐ甚七じいさんの庭へかけてゆき、
「お父さん、かにが来たよ。柿をとりに来たよ。」
そういいました。甚七さんは昨夜した話なんか忘れていたので、
「何だって、かにが来たって、そんなにあわてなくてもいいじゃないか。かには柿なんか食べやしないよ。」
そういって笑いました。すると、
「だって、今にさるが来て、かにとけんかを始めやしないかしらん。」
平作さんがそういいました。それで、
「なあんだ、さるかに合戦の話か。心配ない心配ない。あれはほんとうはかにの柿の木じゃない。平坊の柿の木だ。安心しなさい。安心しなさい。」
そういって、甚七さん始めそこにいた家の人たちみんな一しょに大笑いしました。
ところで、それから何年たったでしょうか。平作さんは十四五にもなっていたそうです。日清戦争というのが起こったのです。その頃の歌だって、お父さんがよくうたってきかせましたのに、
「日清ダンパンはれつして、品川のりだすあずまかん―。」
というのがありますが、明治二十七年八月のことだそうであります。で甚七じいさんは其時三十六かになっていましたが、秋、その柿のみの赤くなり始める頃、召集令が来て出ていくことになりました。おじいさんはそれまでへいたいに行ったことはないので、戦争が始っても安心していたんだそうですが、召集されたのは、輜重輸卒というのでした。馬の背中ににもつをつんで、それを引いてゆく兵たいさんなんです。その頃の歌に、
「輜重輸卒が兵たいならば、電信柱に花がさく。」というのがあるそうですが、そんなに兵たいらしくなく、まるでにもつはこびの人夫のようにいやしめられておりました。しかしおじいさんはけっしてめめしいようすはせず、
「それでは行ってまいります。後のことはよろしくお願いいたします。」
と、しんるいの人や村の人にあいさつし、おばあさんには、
「平作のことをたのんだぞ。」
といい、平作さんには、
「お母さんに孝行しなさい。」
といったそうであります。村の人たちは、めいよの出征というので、もうその頃大きくなっていた柿の木のてっぺんに日の丸の大はたを立て、そこからいくすじもつなを引いて、それに小ばたをむすうにつけました。柿の木は柿の木で、その枝いっぱいに赤やきいろのみをすずなりにならせていましたので、その出征の日のかざりつけは、とてもにぎやかで、遠くの村からでも大へんなお祭りのように見えたそうです。
甚七さんはたくさんの人の行列に見送られて家の門から馬にのっていきました。その前には大だいこ、小だいこ、その前にはよこ笛をならす楽隊が歩いていました。ヒュール、ヒュール、オットット、ドーン、ドーン、オットット。楽隊の音はそうひびいたそうであります。国道のとうげをこし、林の中を通り、三軒ばかり家のある村ざかいの棒杙の立っている所で、見送りの人たちはばんざいを三どとなえました。そしてそこに立って、いつまでも見送っていました。平作さんと、お母さん、―甚七じいさんのおよめさんですね、―その二人と他に二三人のしんるいの人たちはそれからまだ十キロもある鉄道のえきまで見送って行きました。汽車が出る時、平作さんのお母さんが、小さいこえで、
「かえって来てくださいね。」
といったそうです。そうしたら甚七さんが、「 うん。」とこっくりしたといいます。平作さんは何もいえず、ただおじぎをして別れました。汽車が出て、遠くに見えなくなってしまうと、平作さんのお母さんが、平作さんの肩をつかまえて、声をあげて泣かれたそうです。平作さんはそれでも歯をくいしばって、泣けてくるのをこらえました。
その明くる日からしかし平作さんのお母さんは人が変ったように、そうです、まるで男のようになって働きだされたそうです。だってもう稲のかり入れ時だったのです。朝はいつ起きるのか、平作さんが目がさめた時はもうお宮へ行って、お百度をふんで、甚七さんの無事にかえって来るのを一心にお祈りし、そして御飯をたいておられたというのです。平作さんはお母さんのこのはげしい気性にはげまされて、これも一生けんめいに働いたそうです。ところが、それから二月とたたないうちに、まだ甚七さんの手紙も来ないのに、もう戦死のしらせがありました。お母さんがさぞ泣かれることと思って、平作さんは身体がふるえるような気がしたそうですが、お母さんは泣かれませんでした。しらせを持って来た役場の人に、
「かくごはしておりました。」
といわれました。しかしその夜、一ばん中、いつ目がさめても、お母さんは床の中でぎゅうぎゅう歯ぎしりをするように泣いておられました。だけども、お母さんは明くる日起きると、もう男のようになって、それまでと少しも変らず、はげしい働きをせられました。いいえ、前よりももっともっと働くようになられました。
それから五六年、そのお母さんの働きについて、平作さんも一生けんめい働きました。平作さんが二十になった時、お嫁さんをもらいました。するとその明くる年子どもが生れました。これがぼくのお父さんで平太というのです。だから平作さんはぼくのおじいさんですね。
ぼくのお父さんの平太が生れると、おじいさんは柿の苗を買って来ました。これはもう書きました。そして川のふちに、平作じいさんは、自分の柿とならべて植えました。その頃そのおじいさんの柿の木は植えてから二十何年もたっていたので、毎年何百とみのつく、それはりっぱな柿の木になっていました。
ところが、平作じいさんが二十五の時、また戦争がはじまりました。明治三十七年二月のことであります。日露戦争だというのです。その時ぼくのお父さんの平太はまだ五つだったそうです。また、召集令が来ました。甚七さんと同じやはり輜重輸卒でした。五月、遠い山の雪が消え、林にわらびのもえ出る頃、そうです、柿の若葉の美しい頃、平作さんはまた馬にのって、たくさんの人に見送られて、家の門から出て行ったのです。そのおじいさんの柿のてっぺんに大きな日の丸のひるがえったのは、甚七さんの時と同じでした。そこからつなが四方へひっぱられ、それにむすうの小ばたがつけられたのもやはり同じことでした。しかしお父さんの、その時五年にしかならない小さい柿の木にも、同じに日の丸の旗が立てられ、小ばたも少しばかりつけられていたそうです。五つのお父さんがこれを見て、
「坊のハタ、坊の柿の木。」
といって、大喜びしたそうです。
村の人たちはまた村ざかいの、棒杙の所まで送って来て、そこで万歳を三度となえて、おじいさんの馬上すがたがかなたに見えなくなるまで送りました。おじいさんのお嫁さんとぼくのお父さんと、二三人のしんるいの人は十キロ先の鉄道のえきまで送ったのです。汽車の出る前、おじいさんのお嫁さん、ぼくのおばあさんが、やはりおじいさんにそっと言ったそうです。
「平太がかわいそうですから、どうかぶじにかえって来てください。」
しかしおじいさんは涙ぐまれたまま、これには返事をせられませんでした。その代り、お父さんの顔をのぞき込んで、
「平太、お母さんに孝行するんだよ。」
そういわれました。
それから半年ばかり、おじいさんのたよりは一つもありませんでした。おばあさんは二十四だったそうですが、甚七じいさんのお嫁さん、ぼくのひいばあさんの働かれたと同じように男のようになって、牛を使えば馬も使い、ほんとにてぬぐいではちまきをして、たんぼへ出られたそうです。すぐ田植えだったのです。
しかしそんないそがしい間にも、どこからかかわらでできたホコラ―小さいお宮の形をしたものがあるでしょう。―あれを買って来て、おじいさんの柿の木の根元にすえ、その前に朝ばんせんこうをたてられました。甚七じいさんのカタミの柿の木ですから、それには甚七じいさんのれいがこもっているように思われたのでしょう。だからその下にホコラをまつっておけば、甚七じいさんがそこに来て、すまわれ、朝晩の祈りをきかれるように思われたのかもしれません。だからまたきゅうりやなすの初みのりはかならずそのホコラの前へそなえられました。
ある時など、そこへ家のにわとりが初めてうんだ卵を一つそなえられたそうです。が、するとへびがどこからかやって来て、これをのもうとしていたそうです。するとこれを見つけて、お父さんが、
「こらーっ、これはおじいさんの卵だぞーっ。」
とぼうを拾って、へびをたたこうとしました。おばあさんはこれを見ると、
「これこれ、平太、そんなことをするもんではないよ。」
とたしなめられたということです。たとえみにくいへびであっても、これを大切にしておけば、どこかでおじいさんにおんがえしをしてくれ、いのちを助けてくれるようなことがあるかもしれない。これをくようというのだとおしえられました。でもそんなにしておばあさんがおじいさんのためにいのり願われたかいなく、明くる年、明治三十八年三月、奉天という所の戦争でおじいさんは死んでしまわれました。甚七さんのお嫁さんと同じに、その知らせがあった時、おばあさんは涙一つこぼさず、
「かくごはしていました。」
といわれましたが、そのばんやはり床の中で、ぎゅうぎゅう歯をくいしばって泣かれました。それから二十年たって、ぼくのお父さんがお嫁さんをもらって、子どもが出来て、また柿の木を植えて、その柿がなる迄、しあわせなことにわが日本国にも大きな戦争がありませんでした。その生れた子というのがぼくなんですが、ぼくが七つになるまで家には何ごともなく幸福に育ちました。
ところが、四年前の十二月八日、今度の大戦争が起ったのです。お父さんはもうその時四十からになっておられ、この戦争にゆくことはないだろうといっておられました。それが戦争の始った三年目、十八年の秋、柿の実の赤くなり出した時、召集令が来て出ていかれました。家ではまたお父さんの柿の木の下にホコラをつくり、お母さんもぼくも一生けんめい朝となく晩となく、お父さんのごぶじをいのりました。平作じいさんの柿の木の下にあるホコラにも同じようにお供え物をして、お祈りしたことはいうまでもありません。しかしやっぱりお父さんは戦死せられました。出征後一度もたよりがなくて、どこでどうしておられるかわからなかったのですが、戦争がおわった近頃、お父さんは南方へいく途中の船が沈んで、三年も前に死んでおられたことがわかりました。
「二度あることは三度あるというからねえ。」
と、お母さんはいわれて、三年間すっかりかくごしておられたようでした。それでそんな知らせがあっても、歯をくいしばって、泣かれるようなことはありませんでした。しかし、
「三度あったことを四度あるようにはしたくないものだ。」
と、この間お母さんはまたホコラを一つ買って来て、ぼくの柿の木の下にすえ、しきりに手を合せておがんでおられます。きっとぼくをぶじに大きくして、幸福な一生を送らせたいというのでありましょう。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763