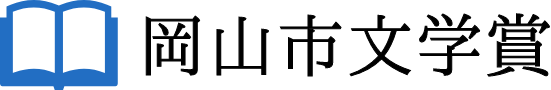狐と河童
「お爺さん、お話。」
田舎から久しぶりに出て来られたお爺さんを取りまいて、善太と三平が話をせがみました。
「さて、困ったなあ。何のお話しようか。お爺さんの知っているのは昔のことばかりでねえ。狐だとか、河童だとか、仙人だとか。」
「その狐、狐、狐の話をして下さい。」
そこでお爺さんが話し出しました。
森の中の大きなかしの木のほら穴に、一匹の狐が住んで居りました。狐は三匹の子狐をつれていました。
ある日、日がてってるのに雨が降って、彼方の森からこちらの丘へ、美しいにじが一本空の上にかかりました。
「おお、これは日でり雨じぁ。急いで、お祭の用意をしなくちあならない。」
おや狐が云いました。
昔から日でり雨の時には、お嫁入りの行列をつくって、狐はお祭をすることになってました。
「さ、早くいらっしゃい。」
三匹の子狐をつれておや狐は穴を出て行きました。
「お母さん、どこへ行くの。」
一匹の子狐がききました。
「お祭って、何をするの。」
もう一匹の子狐もききました。けれども、おや狐は返事もせず、
「大急ぎ、大急ぎ。」
と、子狐をせき立てて、森の側の池の処へやって行きました。池の水の上にはあめんどろという黄色い水草が一面に浮いていました。
「さ、これをかぶるんだよ。これをかぶって人間にばけるんだよ。お母さんがやるから見ていらっしゃい。」
おや狐は水の中へ入って行きました。そしてちょいちょい頭を水草の中に入れて、そのあめんどろをかぶりました。二三度そんなことをやると、池のふちへと上って来ました。頭から身体へ、肩から腹の方へ、黄色い水ごけのようなあめんどろが一面にくっついていました。そこで、おや狐は寒いんでしょうか。身体をブルルルルとふるわせました。それから首を延して、コンコンコンと鳴きました。
と、どうでしょう。
そこに、子狐達の前に、もう人間のおばさんが一人立っていました。子狐達はビックリして、二三メートルも逃げ出しました。
「お母さんよ。お母さんよ。」
おや狐が云いました。
「お母さんなの。」
一匹の子狐が云いました。
「ぼく、人間とばかり思った。」
もう一匹の子狐が云いました。
「あああ、ほんとにビックリした。」
おしまいの子狐が云いました。
「さあ、お前達もお母さんのとおりをするんですよ。この人は女だからおよめさん、あとの二人は男だから、そうね。何がいいだろう。やっぱりさむらいかねえ。刀をさして、勇ましいから。」
おや狐が云いました。
これを聞くと、二匹の子狐は喜びました。
「いいなあ、ぼく達さむらいだ。刀がさせるんだ。人間が来たら切ってやろう。」
そして二匹の子狐はもうさむらいになったような気で、後足で立って、その辺を歩いたり致しました。ところが、もう一匹の子狐が云いました。
「お母さん、あたし、およめさんになるの嫌や、やっぱり、さむらいになりたいわ。」
「何云ってらっしゃるの。およめさんがなかったら、お祭が出来ないじゃないの。」
おや狐が云いました。
「つまんないの。」
そう云いながらも、それからおや狐に教えられて、子狐は一匹ずつ水の中に入って行きました。そしておや狐の真似をして、水草をかぶって、コンコンコンとなきました。見る間に可愛らしい小さなおよめさんが出来ました。勇しい小さなさむらいが出来まして、三匹とも、とても嬉しく、ニコニコして、たがいたがいに見あいました。中にもおよめさんになった子狐は一番うれしいらしく
「どう、兄さん、おかしくない?」
と、小さなさむらいの前で、前や後に向いて見せました。すると、さむらいの一匹がビックリして云いました。
「ああ、だめだだめだ。後にしっぽが見えてるじゃあないか。」
これを聞いて、小さなおよめさんは自分のしっぽを見ようと、後を向いてクルクルクルクル廻りました。ところが、此時ほかの一匹が云いました。
「そう云う兄さんもだめじゃあないか。後を見て御覧。」
「何だい。君だって同じじゃあないか。」
これで三匹が三匹とも、後を見ようとキリキリ舞いを致しました。そうして自分達のしっぽを見てしまうと、そっとおや狐のおしりを眺めました。そして云いました。
「あれあれ、お母さんだってやっぱりあるじゃあないの。人間にもあったかしらん。」
これをきくと、おや狐が云いました。
「ほほほほ、しかたがないんですよ。しっぽばかりはかくせないの。」
それで四匹の狐達はおかしいしっぽをおたがいに眺めあいながら、はらを抱えて笑いました。
「ほほほほ。」
「はははは。」
ところでおや狐は困ってしまいました。だって、この四匹ばかりでは、およめ入りの行列なんか出来ません。それかと云って、友達の狐や、しんるいの狐は丘をこして、彼方の森へ行かねば居りません。そんなことをしていては、にじがきえてしまうかも知れません。もうだんだんにじもうすくなってまいりました。
「どうしよう。だれか、お祭のてつだいに来てくれるものないかしらん。」
おや狐が云いました。
「やぶの中の狸のおじさんどうだろう。」
一匹の子狐が云いました。
「そうだそうだ。」
それで狐たちは人間にばけてることも、うち忘れて、われ先にかけて、やぶの中へやって来ました。
「狸さん、狸さん、狸おじさん、おいでですか。」
すると、同じやぶの中のいたちのおじさんが云いました。
「狸さんはいないですよ。さっき、川でおひる御飯を食べて来るとかと云って、魚をとりに出かけました。」
「あれあれ、困ったことになったなあ。」
狐たちはらくたんしました。これを聞くといたちが云いました。
「何か御用ですか。」
それで、おや狐が云いました。
「わたし達ね、今およめ入りのお祭をしようってところなの。すると、行列のかずが足りないんです。狸さんにたのみに来たのですが、おじさん、一つ、どうでしょう。行列に入って下さいませんか。」
すると、いたちが云いました。
「へへへへ、そりゃだめです。わたしは人間にばけられないもの。もぐら君にでもたのんで御覧なさい。」
「じゃあ、もぐらさん、もぐらさん。」
狐はもぐらを呼びました。すると、もぐらがやぶの中の土の穴から、そっと鼻先をのぞかせて云いました。
「だめだめ、狐さん、ぼくもだめです。ぼくはこの土の中から出られないんです。」
せっかくお祭しようというのに、狐はほんとに困ってしまいました。
「どうしよう。どうしよう。」
四匹はたがいに云いあいました。
お爺さんはここ迄話して来ると、たばこに火をつけました。
「だいぶん長く話したから、ここらで、ちょっと一ぷくさせて貰おう。だが、どうだい。これから狐がどうすると思うね。」
お爺さんがそう云いますと、三平が云いました。
「お爺さん、それよりか、ぼく、そんな狐を一匹ほしいと思うな。箱の中にかっておいて、いろいろなものにばけさせたら、かつどうなんか見るよりきっとよっ程面白いな。」
すると、善太も云いました。
「それよりか、お爺さん、ぼくは、そんな狐がどうして人間にばけられるか、そこんところを習いたいと思うな。そうしたら、人間だって、ずいぶん面白いことが出来るでしょう。」
これには、狐でなくて、お爺さんの方がよわりました。だって、お爺さんの幼いころは子供達はみんな狐をおそれました。いえいえおそれるどころでなくばかされたものだって、何人かいたのです。それなのに、今の子供はその狐を箱の中にかって、ばける方法を習いたいというのです。これではお話になりません。そこで此度は河童のお話をすることにしました。
「河童というもの知ってるか。」
まずお爺さんはききました。
「カッパ、知ってるとも、あの雨の降る時なんか―。」
三平が云いました。
「だめだめ、そんなカッパじゃあないんだ、じゃあ善太は―。」
お爺さんは善太の方に向きました。善太もちょっと考えました。
「雨ガッパでないとすると―。」
こんなことを云って居ります。そこでお爺さんが云い出しました。
「河童というのはね、丁度子供くらいな身体をしていて、頭に皿をかぶっている。まあ、水の中に住んでいる、云わば、おばけ見たいなものなんだね。深い淵などにいて、泳ぎに行ってる子供なんかを、水の底に引き入れる。」
「へへえ、悪いおばけなんだね。」
善太が云いました。
「そう、悪いおばけなんだが、頭にかぶってる皿には、いつも水が入っていてその水のある間はとてもげんきで、その水がなくなると、スッカリ弱って、死んだようになってしまう。」
「へへえ、面白いおばけだなあ。そんなおばけ、ぼく、見て見たいなあ。」
善太が云うと、三平もこれについて云いました。
「そうだ、ぼくも、そんなおばけ一匹ほしいや。お爺さん、田舎にまだそんなのがいるんですか。」
「いいや、それがおしいことに、一匹もいなくなってしまった。狐だって、もう人をばかすのなんか、一匹だっていないんだよ。なぜかって云うと、世の中がすすんで来て、人間がみなかしこくなった。じつは、昔だって、そんなものはいなかった。それなのに、みないるように思っていた。今の人はそんなものがいないということを、子供達まで知るようになった。ね、昔は野山にそんなものがいたのでなくて、人の心にすんでいたんだ。人の心にいなくなると、野にも山にも、狐も河童もいなくなった。ね、それでお爺さんのお話もおしまいです。」
お爺さんはそう云うと、またたばこをスパリスパリとすいました。
「そうか、何だい。」
善太と三平が云いました。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763