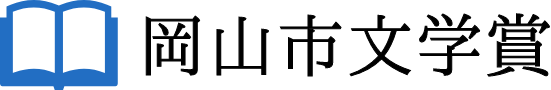「桃の実」―戦後の状況と桃の実について考える―
(初収録単行本 『桃の実』1947(昭和22)年12月 東西社)
(収録本 『坪田譲治全集 第8巻』 新潮社)
ノートルダム清心女子大学 3年 阿部美里
坪田譲治の童話「桃の実」は、終戦より2年後に発行された童話集『桃の実』に初収録されており、作中に「このごろふくいんのへいたいさんが次々と帰ってくる」という記述があることから、この作品が書かれた年代は戦後間もない1945(昭和20)年から1947(昭和22)年の間であると考えられる。私は、かねてから太平洋戦争についての興味があったため、この作品を読み解くうえで、復員兵が戻ってくる終戦後の時代背景を詳しく知ることによって、どのような読みができるか、また、この作品に登場して人々から注目されている「桃の実」がどういった意味をもつのか、ということについて考えた。
この作品は、「山の林の中に一本の桃の木がありました」という文から始まる。その木には立派で美しい桃の実がなっていた。子どもたちはその桃の実を見て「てんぐの桃」「きつねの桃」「ばけ桃」などと空想し、笑いながら道を走り去っていく。それから間もなく桃の木のそばを通りかかったおじいさんは、その美しい桃の実を見て、戦争に行ってもう3年も便りのない息子にこの桃を見せてやりたいと思う。その後3人の青年がおじいさんの方に歩いてきて、おじいさんに獅子舞を披露するが、おじいさんはその間も息子のことを考えている。踊りが終わると、おじいさんは青年たちと一緒に木のそばを後にした。それから何日か経つと、みよ子、四郎、八郎の3人がまた桃の木のそばを通りがかったが、もうその枝に実はなっていなかった。しかしその代り、枝には白い3羽の小鳥がとまっていて、子どもたちは桃が小鳥になったのではないかと言って、神秘的な出来事についての想像を膨らませるのである。
この作品を研究するにあたって、「復員」について調べてみると、石川逸子著『無名戦没者たちの声』(1989年7月 岩波ブックレット)によれば、当時の国民には戦争が終わってしばらく経っても、徴兵された家族がいつ帰ってくるのか、それどころか生きて帰ってくるかすらもはっきりと知ることができなかったそうだ。階級によって後の復員船に回されたり、運よく船に乗れても、爆撃を受け海に沈んでしまったりすることもあり、戦争が終わってからも安心することはできなかった。『昭和の戦争 ジャーナリストの証言 7 引揚げ』(松岡英夫監修 1986年3月 講談社)によると、中国の敦化(とんか)に残っていた日本兵が、ソ連兵に騙され、列車でシベリアに送られて、強制労働を課せられることもあった。『朝日新聞』(1947年1月30日)によれば、1月の時点で復員者が518万人であるのに対し、未復員者がまだ140万人もいたのは驚くべきことである。また、『朝日新聞』(1946年8月4日)によれば、遺骨として浦賀の上陸地支局に帰ってきた兵隊も、14000柱のうちなんと半分が受取人不明であったという。そして、作中に登場するおじいさんの息子が残っているという小スンダ列島には、『朝日新聞』(1947年1月30日)によれば、1月の時点で31人の兵隊が日本に引き揚げることができていなかった。
このような当時の状況を考えて、この作品の描写を見ると、息子が生きていると思い込もうとしているおじいさんが「そうだ、むすこは今ごろこんなにてっぽうを草の中にほうり出し、やしの林の中か、コーヒーの木の下に、こんなにして国のことを思っているだろ、そう、そうにちがいない」と考えている描写が注目される。ここから、おじいさんは、3年もの間、息子からの連絡が一切ないなかで、他の復員兵たちが帰ってくるのを見ることによって、まだ息子も生きているかもしれない、生きているに違いないと自分に言い聞かせて、息子が死んだという可能性から目を背けようとしていることが読み取れる。そして、3人の子供たちが遊んでいる場面の「ワッハッいいながら逃げて行きました」という記述に見られる子どもたちの無邪気に遊んでいる描写や、3人の青年が獅子舞を踊る場面で獅子頭が「大きなその金の目を日にキラキラかがやかせたりいたしました」などの獅子舞の輝いている描写が、おじいさんの悲しみをより顕著に浮き上がらせているように感じられる。
ここで、この作品の作者である坪田譲治自身の戦争体験について調べてみると、『坪田譲治全集 第12巻』(新潮社)に「息子帰る」(初出『息子かえる』1947(昭和22)年10月 青雅社)と「正太復員」(初出『故里のともしび』1950(昭和25)年11月 泰光堂)という二つのエッセイが掲載されている。同全集の「年譜」を確認すると、譲治は1943(昭和18)年7月に海軍報道班員として徴用され、さまざまな場所を転々としながらスラバヤに向かっている。また、譲治の3人の息子たちも同様に徴用され、長男・正男と次男・善男は小笠原に、三男・理基男は横須賀に駐屯していた。終戦後には、譲治は信州の野尻湖畔に疎開し、3人の息子たちもみな無事に復員することができている。「息子帰る」と「正太復員」のエッセイには譲治が疎開し、息子たちが復員するまでのことが書かれているのだが、そのなかで譲治は「桃の実」のおじいさんと同じように息子たちを思う心情を綴っている。疎開先の野尻湖畔は戦前から譲治が毎年のように釣りに行くところであり、息子たちも何度か休暇で訪れたことがある場所であった。疎開後も譲治はそこで釣りをしながら、昔の息子たちの「姿がチラチラするような思い」(「息子帰る」)がしたと書いている。したがって、「桃の実」のおじいさんの心情は、譲治自身が終戦後に感じたように、まだ戻らない息子たちを心配したり、ともに過ごす実感を空想したりする思いを投影していると考えられる。
次に、この作品の「桃の実」が「てんぐの桃」や「不老不死の桃」として神秘的に人々から捉えられ、しかも題名が「桃の実」であるのはなぜだろうかという点について考えるために、日本における「桃」の描かれ方を調べてみると、『現代語訳古事記』(蓮田善明訳 2013年9月 岩波現代文庫)の中でイザナギとイザナミの神話に桃が登場していた。『古事記』では、イザナギノ命はイザナミノ命を黄泉の国から連れ戻そうとするが失敗し、8の雷神と黄泉の国の大軍に追われることになった。イザナギノ命は黄泉の国と地上の境にある黄泉比良坂の麓まで逃げ、「その坂下の桃の実を3つ取って」雷神たちに投げつけて撃退した。このことによってイザナギノ命は桃の実に助けてもらった礼を述べ、「この後も、わが国に暮らしている者どもが窮境に陥っている時には、どうか今日のように助力を与えてやってくれ」と頼み、「オホカムヅミノ命」の神名を桃に授けたとされている。また、『日本国語大辞典 第2版 第12巻』(佐藤憲正 2001年12月 小学館)の「桃」の項目を確認すると、「古くから災厄を除く樹木とされていた」と書かれていた。このことから「桃の実」は古来より邪気を払い、人々を救う存在とされていたことが分かる。さらに、昔話として語り継がれている「桃太郎」についても調べてみると、『江戸の子どもの本 赤本と寺子屋の世界』(叢の会 2006年4月 笠間書院)に、桃太郎の誕生には「桃から生まれる果生譚」と「桃を食べて若返った爺婆から生まれる回春譚」という2つの型があると書かれている。江戸期の「桃太郎」はほとんどが回春譚の方であり、当時の赤本にも出産の様子が描かれている。また、中国には食べると不老不死になるという桃の伝説が存在し、古来より桃が生命力の象徴であるとされている。したがって、この作品における「桃の実」も、戦後未だ残っている戦禍を遠ざけ、生き残った人々に強い生命力を与えるものとして描かれていると考えられる。また、3人のうちの八郎が山の林の中に生えている一本の桃の木を見て、「あの桃、てんぐの桃なんぜ」と言っているのは、戦争という厳しい現実を描きながらも、「てんぐ」という伝説上の存在を登場人物の子どもに語らせることによって、桃の幻想的で神秘的な雰囲気が醸しだされていると思われる。
以上のことから、この作品において、おじいさんは戦争に行った息子を想い、過去に心を向け悲しみから抜け出せていないのに対し、子どもや青年たちは未来への希望に向かって生き生きとして描かれているが、その両者を「桃の実」がつないでいることがわかる。さらに「桃の実」は、おじいさんたちのように戦争を生き延びた人々を慰め、生きる力を与えるものとしてこの作品に登場していると考えることができる。したがって、私は復員について調べ戦後の状況からこの作品を読み深めることによって、戦争によって当時の大人と子どもがそれぞれ感じていた死への不安と、その不安に駆られながらも人々が桃の実の力によって支えられ懸命に生きている様子とを、より深く感じることができた。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763