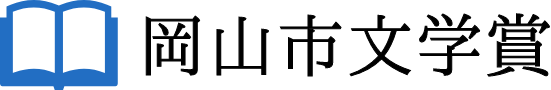「狐」―甚七郎が伝えたかったことを民間信仰より考える―
(初出 『赤い鳥』昭和11(1936)年7月号)
(収録本 『坪田譲治全集 第7巻』新潮社)
ノートルダム清心女子大学 大学院博士前期課程 1年 谷村未央
坪田譲治の童話「狐」は、児童雑誌『赤い鳥』の昭和11年7月号に掲載された。まず、この作品についてあらすじを紹介したい。
武士である甚七郎の家は江戸時代の岡山の町に近い田圃の中の村にあり、その家には12歳になる柳太郎が預けられ住んでいた。柳太郎は、「剣術がとても強かった」甚七郎から長船という刀をもらう。柳太郎は刀をもらった嬉しさから、甚七郎が信頼する下男の金十に見せに行った。そこで、金十は柳太郎に巻藁を切ってみないかと提案する。柳太郎は巻藁を切ってみようとするが、切ることができない。しかし、菜園にあったけし坊主を切ることができた柳太郎はやる気を出し、剣術を甚七郎に学ぶのであった。こうして、15歳の春になった柳太郎は、巻藁を上手に切ることができるようになっていた。
ある日のこと、刀で本物の生き物を切ることを試したくなった柳太郎は、金十に勧められて大川の橋の上で大狐を捕ることにする。柳太郎は、さらに金十から刀ではなく棒を持っていくように言われ、「それもそうだ」と思い、その夜の12時過ぎに棒を腰に差して大川の橋の上に行った。橋の上に立って狐が現れるのを待っていると狐の声が聞こえた。柳太郎は、狐が金十に化けたと思い込んでいるので早速その狐を捕ろうとするが、「ま、まあ、お待ちなさい。それが剣術ばかりではいけないというところでございます」と言われる。柳太郎はその言葉が金十本人だと思われたため、狐ではなく金十本人だと思う。そこで、金十と一緒に家に帰るが、家が近くなったときに金十の姿が見えなくなり、狐の鳴き声が聞こえた。柳太郎が家にすごすご帰ると、玄関に甚七郎が待っていた。甚七郎は柳太郎に対し、「あれはおじいさんがやったのだよ。狐ではないのだよ。な。剣術ばかりでなく、胆力ということも教えてあげようと思ったからだ。わかったかい」と伝えて、作品は終わる。
この作品で考察したい点は二点ある。一点目に、甚七郎が狐を使って柳太郎になぜ「胆力ということも教えてあげようと思った」のかについて民間信仰の観点から考えたい。二点目は、柳太郎が狐を捕ろうとしたときに、「剣術ばかりではない」と甚七郎と金十が柳太郎にたびたび言っていることから、甚七郎が柳太郎に真に伝えたかった武士の精神について解明していきたい。
まず、一点目の甚七郎の言葉について考えると、甚七郎は「胆力ということも教えてあげようと思った」と言っていることから、金十が柳太郎の前に現れたと解釈できる。「胆力」とは、「ものに恐れず臆しない気力。度胸」(『広辞苑 第六版』2008年1月 岩波書店)とある。胆力は経験を通して身につくものである。柳太郎が勇気を出して金十を捕ることができるか甚七郎は試したのだろう。加えて柳太郎は15歳であり、江戸時代では元服をする年頃である。甚七郎は柳太郎に一人前の大人、そして一人前の武士になってほしいと思い、ちょうどこの元服を行う時期に計画を遂行したのだろう。甚七郎が、実際は「あれはおじいさんがやったのだよ」と言っているように、甚七郎が計画を立てて、金十と一緒に柳太郎の度胸試しをしているのだと考えられる。
それでは、甚七郎が柳太郎に「胆力」を教えようとするとき、なぜ狐を通して行おうとしたのだろうか。ここで考慮しておきたい点は、柳太郎の狐に対する考え方と、甚七郎と金十の狐に対する考え方が異なっているであろうことである。
まず柳太郎の場合は、狐を「人間に悪いことをする奴」だと思っている。その「悪いこと」とは、狐が家畜を荒らす存在であることと、また人を化かす存在だと思っていることからきているのだろう。作品の冒頭にも、村の近くには「ときには、河童などもいたということであります」と描かれ河童の存在が信じられていたように、狐が人を化かすということも信じられていたことが推測される。
一方の甚七郎や金十の狐に対する認識を見ていきたい。もちろん、家畜を荒らしたり、人を化かしたりする認識はあっただろう。しかし、害獣以外の認識もあったのではないだろうか。坪田譲治が生まれ育った岡山県は稲荷信仰の盛んな土地であり、最上稲荷がある。なお、坪田譲治の家の宗教は日蓮宗であるが、最上稲荷も日蓮宗であり、坪田譲治が「狐」を執筆するうえで、最上稲荷を意識していた可能性もあるのではないだろうか。資料を見てみると、稲荷信仰の中で狐は重要な存在になっていることがわかり、吉田清著『稲荷信仰の研究』(1985年5月 山陽新聞社)では、稲荷信仰について以下のように記されている。
狐は食物神の化身あるいは稲女そのものである。これが宗教観念の変化により食物神や稲女のお使い、つまり稲荷神のお使いだと考えられるようになった。しかしながら、庶民にとっては抽象的な稲荷神よりも、お使いである狐のほうがはるかに身近で気兼ねなく願いを聞き入れ、叶えてくれるものだと考えたのだろう。狐は眷属神という一段低い位に身分を落としながら、実はかえって多数の庶民の支持を得たのである。 (傍線は筆者による。以下同)
ここで、狐が「稲荷神のお使い」であり「願いを聞き入れ、叶えてくれるもの」であると考えられていることから、そうした素朴な信仰を持っていたと考えられる江戸時代の甚七郎は、狐をありがたがり、神聖なものとして考えていたことがわかる。そして、甚七郎がこうした狐の力を頼みにしてこのような計画を立てたのは、柳太郎にとって、真実を見極められる機会となり、また物怖じしないための度胸をつけられるようにとの願いを、神聖な狐に託したかったためであろう。
以上のことから、甚七郎は元服を前にした柳太郎に一人前の大人になるのと同時に、一人前の武士になってほしいという願いから、「稲荷神のお使い」であり、願いを届けてくれる神聖な生き物としての狐による度胸試しを行ったと考えられる。
次に、二点目の考察として、甚七郎と金十が、柳太郎に「剣術ばかりではない」と度々言っている真の意図について考察するうえで、そこで伝えたかったと思われる武士の精神について考えていきたい。この作品の時代設定は江戸時代だと前述したが、江戸時代の武士の精神について調べてみると、二つの重要な観点があることがわかった。笠谷和比古著『武士道 その名誉と掟』(2001年8月 教育出版)では以下のように記されている。
徳川時代における武士道の性格を考えるうえで留意しなければならないことは、その思想であれ、その行動形態についてであれ、それらが二つの大きな流れの合流点において形成されていることである。一つは、中世武士のエートスとも言うべき「弓矢取る身の習い」であり、いま一つは近世に入って大きな影響力をおよぼすにいたる儒学、ことに朱子学の倫理観である。
この記述から剣術のほかに儒学や朱子学が重要な位置を占めていたことがわかる。「狐」の本文の中に「青山甚七郎は座敷で机に向かって、昔の支那の本を読んでいました」という文章がある。「昔の支那の本」は、中国の本、つまり漢籍であると考えられる。具体的な書名は不明なので断定はできないが、儒学や朱子学の知識を漢籍から得ていたと考えられる。
しかし、甚七郎が言った「剣術ばかりではなく、胆力ということも教えてあげようと思った」という言葉から、武士にとって剣術や教養とは別に必要なものがあったと考えられる。甚七郎の言葉から推察するに、柳太郎には「胆力」がないと思われるが、剣術以外の力として「胆力」は必要なことなので、甚七郎が柳太郎に「胆力」を教えてあげようと考えた、と解釈することができる。笠谷氏は同著で「葉隠」の真意についての説明の中で例を挙げて次のように述べている。
例えば、かれが仕えている主君に誤った行動や暴虐な振る舞いがあったとき、これを諫め、あるいは異議を申し立てて正しい人間関係、社会秩序を回復するように行動することも武士の道である。しかし、主君の命令や意向に対して異なる意見を表明することは勇気がいるし、またさまざまの不利益や危険をともなうものでもある。
武士にとって、日々の生活の中にも勇気が必要であったことがわかる。この「勇気がいる」ということは、甚七郎が言った「胆力」につながる。武士にはもちろん剣術の力が必要だった。柳太郎は剣術の腕前は上達していたが、精神面ではまだ足りないと甚七郎は考えていたのだろう。
以上のことから二点目の考察については、甚七郎が柳太郎に剣術ばかりではないと言っていたのは、剣術よりむしろ重要な武士の精神である「胆力」が必要だと考え、柳太郎にその「胆力」を身につけてほしいと真に望んでいたといえる。
こうして甚七郎は、孫の柳太郎に武士として必要な力を身につけてほしいという願いから、将来的には甚七郎の家を継ぐであろう柳太郎に、武士の家を継がせても大丈夫な力があるかどうかを確認し、その真の力をつけさせようとしたのであろう。
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763