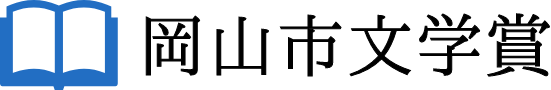「正太の故郷」―作者の故郷へのまなざし―
(初出 『地上の子』1921(大正10)年5月)
(収録本 『坪田譲治全集 第1巻』 新潮社)
ノートルダム清心女子大学 大学院 博士後期課程 2年 轟原麻美
坪田譲治にとって、故郷とは何であろうか。
小説「正太の故郷」では、帰郷した主人公・正太の故郷観が、故郷での出来事を通して変遷していく様子が描かれている。そこで、この作品における正太の故郷観が変化する過程を見ていこうと思う。
作品の冒頭で描かれるのは、正太の心の支えとなっていた故郷の姿であった。正太は東京で文筆業に励んでいたが、しかし生活が成り立たないのであれば、帰郷して生計を立てるための仕事をしてもよいと考えていたのである。そうまで思えるのは、思い出の中の故郷が美しかったからこそであった。具体的には、その理想郷とも言える故郷の姿は、7歳のときの正太の思い出のなかの故郷であった。
その思い出には7歳の正太と、彼の祖父が登場する。そして正太と祖父の周りには、常に故郷の豊かな自然があり、様々な生き物が存在している。祖父と空を眺めたり、川で漁をししたりすることによって、正太は自然の中に生きる生物に関わっていくことを知った。言い換えれば、祖父は正太に対して、自然豊かな場所に生き物がいると認識させることのみに留めず、人間が積極的に関わっていく在り方を教えたのである。
ある日、祖父は正太に鳶がどう鳴くか問うた。この問いに答えることはさして難しくないだろう。7歳の正太でも鳶が「ピーロロ」と鳴くことは知っていた。そこで祖父は正太に重ねて「じゃあなぜ鳶が鳴く」と問うた。正太はこの問いに答えることが出来なかった。そんな正太に祖父は親不孝な鳶の物語を聞かせた。その物語における子供の鳶は母親の鳶の言うことの逆ばかりをして困らせていたという。たとえば北へ行くように言えば、南に飛んで行くといった具合である。あるとき自身の死期を悟った母親の鳶は、自身の死骸を河原に埋めるように言づけた。母親は山や林に埋めてもらうことを期待したのである。しかし母親の死に直面した子供の鳶は自身の親不孝を悟って反省し、母親の最期の言葉に従って河原に埋めた。すると大雨が降り、川が増水してしまい、子供の鳶は母親の遺体が流されてしまうのではないかと心配でならなくなった。だから鳶は鳴きながら、空の同じ場所に輪を描いて飛ぶのだという。
鳶はなぜ鳴くか。この理由を想像する力を、祖父は正太に教えた。想像力をもって生き物に接することで、彼らはより人間に近しい存在となる。正太が思う良い故郷とは、このように、自然と生き物がそこにあって、生きとし生けるものに対して想像力を働かせることのできる故郷であったといえるのではないか。
しかし、成人して東京から帰京した正太が目の当たりにしたのは、故郷の変わり果てた姿であった。思い出の中にあった自然は環境整備によって失われ、生き物たちが住めるような環境ではなくなってしまっていた。正太は故郷に対して失望する。第一の理想とする文筆業が成り立たずとも、故郷であれば別の仕事でも厭わないと正太は考えていたのだが、現在の故郷の有り様に直面し、そのような思いはたちまち消えてしまった。
そんな正太に、故郷の実家に暮らす実兄は次のように言った。「歳をとると、人間には故郷なんていういい処はなくなるよ」と。この言葉に正太は頷けなかった。故郷はなくならない。そう感じる正太は、ひとつの考えに至る。「故郷というものは固定した一つの処にあるのでなくて、それは歳月と共に移って行く」と考え、かつての故郷を故郷と思えなくなった正太は、ここではないどこかにある故郷を、心の中で求めるようになっていくように思われる。
しかし、自然の中に自身の身を置くことに価値を見出す正太の故郷観は、ある出来事によって、もう一段階、変化を遂げることとなる。それは、甥の平三の存在によってであった。
正太は、平三が物置で見つけた鼠の子供を飼う遊びをしようとしているのを見つけ、自身もその遊びに混ぜてもらう。二人は子鼠のために小屋を作り、寝床を整え、餌をやった。もはや故郷でなくなった土地で働く気も起きず、鬱々としていた正太は、平三の楽しそうな様子を見て、ここで新たな気づきを得るのであった。それは「平三は今ここを故郷として生きている」ということであった。正太にとって、今この場所はもはや何でもない土地である。思い描いてきた理想の故郷を織り成す自然や生き物の姿が失われた以上、正太はここを故郷と慕うことはできなかった。しかし平三は、今ここにある自然や生き物を通して遊び、楽しみ暮らしているのである。正太は平三と鼠を介して遊びをすることで、自身の新たな故郷との関わり方を見出したといってよかろう。それはかつて、正太の祖父がそうであったように、自身にとっては望ましい、理想的な故郷ではなかったとしても、新たな世代にとっての故郷の中において、自身が積極的に関わっていくというあり方である。このことに正太は気づき、若い世代と新しい環境を見守り共に生きていくという、かつての故郷での新たな立ち位置を見出したのであった。
しかし、この新しい故郷を若い世代と共有し楽しむという、正太にとっての今の故郷の価値は、あっけなく潰えてしまう。なぜなら先に「歳をとると、人間には故郷なんていういい処はなくなる」と述べた実兄によって、鼠小屋ごと子鼠は潰され殺されてしまうからである。このむごたらしい出来事に、正太は取り立てて発言をしない。ただ、「鼠はまたとれるよ」と平三を慰めるのみであった。しかしこの出来事ののち、正太はこの土地を発つのである。平三は叔父である正太が故郷を立った理由について、「山の向うで鼠を飼うため」だと周囲に話した。それは鼠の出来事の直後、正太が平三にここを去る意思を告げ、「遠い遠い、あの山の向うで鼠を飼うの」と言ったことによる。正太のこの言葉の真意は、果たして何であったか。
鼠を飼う遊びは、正太と平三とを世代を超えて結びつけた共通の楽しみであった。それはかつて、正太と祖父が自然を介して交流を重ねたことに似ていると言える。「あの山の向うで鼠を飼う」とは、どこかは分からないが別の土地において、若い世代の故郷を尊重し、彼らの故郷に関わっていくことで、そここそを自身の故郷としたい、そういう考えが現れていると推察した。
正太が大切にしていた故郷は、もはや今この土地にはなかった。かつての美しい故郷の面影は失われている。そして故郷との新たな関わり方が見いだせた矢先に、心無い人によって失われてしまった。しかし、ここに住む人すべてが心無いわけではない。平三のように、今ここが故郷だと考える若い世代がいる。彼らがいる限り、故郷は失われない。平三が生き物に関わろうという楽しむ心を失わない限り、鼠はまた取れるのである。
しかし正太はここで、新たな故郷を求め始めたといって良い。正太は、やはり自分自身にとっても故郷と思える土地で暮らしたいという思いを固めたのであろう。その結果として、新たな世代と新たな故郷で暮らすことをやめ、どこか遠くへ去ったのである。
就業せず、どこか別の土地で暮らそうとする正太に、故郷の家族は「何処へ行っても、お前の思うような処などはありゃせんよ。人間はみな同じような人間の中で暮らさなけりゃならないんだ」と忠告する。この言葉に背き、かつての土地を発ったことを考慮すると、正太にとって今、故郷の要素として大切なことは、「人間」であったのではないか。これまでは自然が第一の要素であったが、鼠の一件により、故郷を故郷とするのは人の心だということに気がついたのであろう。思い返せば、祖父の存在、そして平三の存在によって、正太は故郷を見出している。そうであるならば、子供のかわいらしい遊びを、子供の鼠をくだらないと潰してしまう人間の中では生きられないと、正太は認識したのだろう。
正太にとって故郷とは、はじめは自然に重きが置かれていたと言えよう。過去の故郷に思いを馳せ、今の故郷に目をやり、自然は変じていくものだと知った。重要なことは、その土地に住む人間であることを、鼠の一件により正太は気が付いた。故郷とは、自然や時間の経過、自身が年老いることで変わるのではない。その土地に、人がどのような心映えによって生きているのかこそが重要なのである。故郷とは人の心が織りなすものであることを知り、正太は新たな故郷を求めて、かつての土地を去ったのであろう。
さらに、成人した正太が松の樹の上で見た「不思議な鳥」に注目して考察を加えたい。この不思議な鳥とは、正太が鼠の一件の後に見かけた鳥である。作中では、その鳥の正体が明かされることはない。鳥の特徴については「雀のような毛色に白色を処々にまじえ、無花果程しかない大きさの鳥」とのみ記述されている。これらの特徴から、この鳥とは、ノビタキという渡り鳥だと推察される。ノビタキは岡山でも確認された鳥で、本作が成立した大正10年にも存在した可能性が高い。この鳥が飛び立つのを見て、正太は平三に土地を去ることを告げたのであった。正太は、去るノビタキと自分自身を重ねたのだと考えられる。
渡り鳥は、季節の流れに従って、住処を移す。ノビタキの生態は、先に正太が考えた「故郷というものは固定した一つの処にあるのでなくて、それは歳月と共に移って行く」という思いに重なるように思われる。はじめのうち正太は故郷を思うとき、土地と思い出に固執していたと考えられよう。しかし、正太は自分をノビタキという渡り鳥を重ねることで、故郷というものに対して自由な考えができるように変化したのだといえる。心が変化した後の正太にとって、故郷とは、心によって定まるものであり、一所に固執するものではないと捉えられるようになったのだろう。執着していないからこそ、正太はかつての故郷に、またいつか戻ってくることもあるのではないか。ノビタキは、そんな正太の姿と思いを象徴していると思われる。
最後に、本作が書かれた大正10年に着目しよう。当時の坪田譲治は、東京から故郷岡山に戻り、家業(島田製織所)に勤めていた。その傍らで、「正太の故郷」を掲載することとなる同人雑誌『地上の子』を創刊し、小説を発表するなど創作にも臨んでいた。このように、上京中には文筆に取り組みながらも、経済的状況が許さず帰郷するという点が、坪田譲治と正太では共通している。また「正太の故郷」が発表された大正10年までに、坪田譲治は家業の関係で大阪や兵庫に移り住んでいる。坪田譲治の場合は、仕事上やむを得ず居住を移しているのだが、離れることによってこそ感じられ、見えてくる故郷があったのではないだろうか。
さらに、「正太の故郷」の成立の背景には、坪田譲治の子供たちの存在が影響していると思われる。当時の坪田譲治には、4歳になる長男・正男と、1歳になる次男・善男がいた。家業と文筆業と家族、そして自分自身を、坪田譲治は岡山という故郷にあって見つめ、考えを巡らせていたのではないだろうか。このような状況のなかで、坪田譲治は、幼い子供を見るにつけ、故郷というものに対しての想いを、「正太の故郷」という作品に込めたかったのだと考える。
参考文献
『岡山の野鳥』(日本野鳥の会岡山県支部編、山陽新聞社、1988年)
お問い合わせ
スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1054 ファクス: 086-803-1763