
実施団体
NPO法人岡山県精神障害者家族会連合会
協働課
岡山市こころの健康センター
解決を目指す課題
精神疾患は、思春期から青年期に好発するが、本人・保護者・教育機関関係者のいずれも正しい知識を得る機会が少なく、間違った知識による差別意識の形成のほか、病気の早期発見・治療を妨げています。
精神障がいに対する差別や、障がい当事者への対応に家族は孤立・疲弊しており、家族自身が支援を必要とされる状況にあるが、身近に安心して相談できる相手がおらず、多くの家族が、精神疾患に関する十分な情報を得るまでに、発症後3年を要しており、治療や対応の遅れが、当事者のその後の社会参加に影響を与えています。
そして、家族の状況(高齢化による経済的・身体的な不安、世代交代)が、入院中の精神障がい者の地域移行(地域生活への移行へ向けた退院の支援)や退院後の地域定着(安心して地域生活を継続すること)の障がいとなっています。
課題解決の方策
- 中学校の先生を対象とした精神障がいについての啓発活事業への家族ピアサポーター(体験発表)派遣。差別や発症当時の状況を伝えることにより、病気の早期発見・治療を促すとともに、偏見差別の解消をはかる。
- 疲弊した家族の相談を、同じ体験をしてきた家族ピアサポーターが傾聴し、相談を聴くことにより、家族の孤立感を軽減。当事者との接し方についての学習の機会の提供。家族内で当事者を丸抱えする必要はないことを伝え、社会資源の活用を促す。
- 家族ピアサポーターでは対応できない問題については(実際の社会資源の利用など)、関係機関へ繋ぐなどし、具体的な問題解決への道筋をつけるほか、必要な情報が得られる機関の紹介などを行う。
- 行政および関係機関の地域移行・地域定着支援に対して、精神科病院に入院している長期入院者の地域移行等が円滑に進むよう家族側の不安軽減をはかる。
提案書など
事業の成果

「家族ほっとライン」で電話相談を受ける
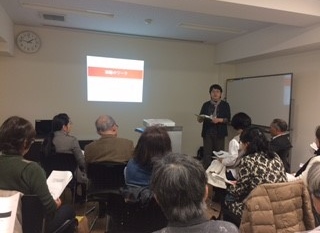
12月16日スキルアップ研修会の様子
- 家族ピアサポーターによる相談支援を行った。
家族相談電話(ほっとライン) 週1回全40日開設 相談44件
家族ほっとサロン 月1日全10日開設 参加者33人
家庭訪問相談 1日実施 1件
同じ悩みを持つ家族同士が苦労を話し合える時間を持つことで、利用した家族はこころの負担が軽減し、自分自身の生き方にも前向きに取り組んでいけるという変化が生まれている。 - 実施団体が別に運営する地域活動支援センター1型の専門職がピアサポーターの助言を行える体制を整えた。
- 家族ピアサポートスキルアップ研修会を12月16日、ゆうあいセンターで開催。アドバイザーとしての役割や活動の事例、コミュニケーションの基本姿勢を学んだ。
成果・実績報告書等
協働事業を振り返って
実施団体からのコメント
どこにも繋がっていなかった家族が、電話相談や家族学習会をきっかけに孤立感を軽減し、正しい知識や対応を話し合い、家族同士の共感や支え合いが生まれてきている。家族ピアサポーター活動の広報には、「通院時に掲示してあるチラシを見た」といった家族もあり、さらに関係機関にも協力依頼を広めていく必要がある。
平成29年度は岡山市自発的活動補助金を受け、引き続き家族ピアサポーター事業を継続していく予定であるが、さらに家庭ピアとしてのスキルアップと、事業の効果を広める努力が求められる。
(NPO法人岡山県精神障害者家族会連合会
協働課からのコメント
家族という同じ立場での支援は、相談の敷居を低くし有効であると考えている。行政だけでは出来ないこの取り組みを家族会と協働して行うことで、より当事者に身近で受け入れやすくなり、効果的であると考える。
今年度の量的実績は目標値の半数という結果になっているが、その点については今後のPRにより、活動が普及・定着し、徐々に実績を上げていくものと考える。
また、相談支援の質についても、ピアサポーター研修の充実を図りながらよりスキルアップされるものと考えており、初年度の実績としては、量・質ともに良好であったと言える。
今後もより多くの家族が家族ピアサポーターとしての研修を受け、活動を広げていき、家族ピアサポーターの活動が、相談支援に留まらず、未だ根強く残っている精神障害者に対する差別・偏見の解消に向けて、自らの体験を語る等、体験者としての活動を期待している。
(岡山市こころの健康センター)
伴走支援者からのコメント(協働の原則の視点から)
「お互いの特性に基づく役割分担がなされていた」(相互理解の原則から)
精神障がい者やその家族に対して専門家・公的機関による支援だけでなく「当事者や家族による支援」を確立・普及させることを目指した意欲的な事業であり、団体の当事者性と担当課の専門性が生かされた役割分担がなされていました。特に今回の協働事業を通じて担当課がピアサポートに対する理解を深められたことで、さらに充実した支援につながっていくことが期待されます。
「目標設定時の情報収集が不十分だった」(目的共有の原則から)
本事業では当初に設定した相談件数と研修受講人数(新規ピアサポーター)の目標数値を達成することができませんでした。ピアサポートに対する周知が十分でない状況においてやむを得ないと感じる反面、定量目標の設定の難しさを実感しており、事前に対象の人数やニーズを把握しておかなければ適切な目標設定ができないことを実感しました。コミュニティから孤立した状況にある方々に情報を届けることは決して簡単ではありませんが、団体のネットワークと行政の有する情報をうまく活用して、少しずつでも支援を広げていただきたいと思います。
(ESD・市民協働推進センター センター長)
