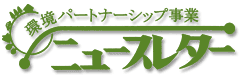
|
第9号
平成15年12月16日 発行 |
|
 年もせまり何かとご繁忙のことと思いますが、風邪などひかれませんようお気をつけください。 年もせまり何かとご繁忙のことと思いますが、風邪などひかれませんようお気をつけください。
さて、第9号のニュースレターができましたのでお送りします。活動の参考にしていただければ幸いです。
 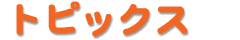
 岡山市環境パートナーシップ交流会 岡山市環境パートナーシップ交流会
岡山市の環境づくりについて考える!
 とき●11/30(日) とき●11/30(日)
ところ●岡山市役所 7F大会議室 今回2回目を迎える「環境パートナーシップ交流会」
おおつ環境フォーラム事務局長の堤幸一さんの取組事例や日頃、環境活動に取り組んでいる市民団体や事業所などの活動発表、パネルの展示、交流会がありました
午前中の中学生・高校生の環境研究発表会では岡山大学の大久保賢治先生のアドバイスも受けました
 今年も和やかに開催 今年も和やかに開催
岡山市環境パートナーシップ交流会は、今回で2回目です。会場では午後一時の開会よりも前から、展示された39点の活動報告パネルを前に、参加者たちの日々の活動の自慢話に花が咲きました。
 活動人数5パーセントの価値と有意義な取組み 活動人数5パーセントの価値と有意義な取組み
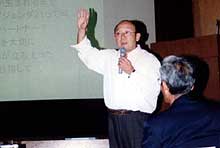 会は小林環境局長の「現在、岡山市でのパートナーシップ事業は834団体31,213人が活動され、岡山市の人口63万人の約5%にあたります。5
%は世界レベルから見ても素晴らしい数字です。市民協働の原点でもあるこの事業で交流の輪を広げてください」というあいさつから始まりました。 会は小林環境局長の「現在、岡山市でのパートナーシップ事業は834団体31,213人が活動され、岡山市の人口63万人の約5%にあたります。5
%は世界レベルから見ても素晴らしい数字です。市民協働の原点でもあるこの事業で交流の輪を広げてください」というあいさつから始まりました。
続いて、おおつ環境フォーラム事務局長の堤幸一さんの「三方よしの協働をめざして」と題しての取組報告です。
『三方よし』とは近江商人の言葉で、「売り手よし、買い手よし、世間よし」つまり世間も喜んでくれないといけないという意味です。おおつ環境フォーラムではこれをモットーに、やりたいことがあれば、人が集まり、やりましょう!と、『市民・行政・企業』の三方が協力し三方ともよくなるよう、地球を守るための活動をしています。
 テーマはいろいろ テーマはいろいろ
 さて、交流会では39団体のパネル参加と14団体のスピーチ発表がありました。スピーチの持ち時間は8分。どのグループも活発に発表されていました。 さて、交流会では39団体のパネル参加と14団体のスピーチ発表がありました。スピーチの持ち時間は8分。どのグループも活発に発表されていました。
地域の用水・歴史・文化にまつわる昔からの行事を復活させ、地域の環境を考えるグループ。児島湖周辺のさまざまな問題に取り組んでいるグループ。昔、身近にいた淡水魚や身近な水辺のある暮らしを取り戻したいと活動するグループ。自然エネルギーを考えるグループ。捨てられたゴミを分別してリサイクルに回しているグループ。自然にやさしい暮らしについての本を出版したグループ。だれでも自らゴミを出しておきながら、複数の産廃処分場の中で暮らさなければいけない、厳しい現実と向き合っているグループなど…、活動はさまざまで言い表せない苦労もたくさんあるのでは、と感じました。
企業での取組はCO2や紙・水の削減は当然のことのように実践されていました。節電・節水は今では常識化しているのではないでしょうか。より高度な再生化の工夫が見られ資源節約に期待がかかります。発表中盤の休憩時間では、あちらこちらのパネル展示の前で積極的に活動の説明をしたり、他の団体に質問したりと交流を楽しんでいました。
 活動を通じて環境を守る 活動を通じて環境を守る
予定通り発表も終了し、途中から参加の萩原市長はあいさつの中で「岡山がアジアの環境保全の拠点になるよう努めていきたい。岡山市ではさらに強く後押しをしていきます!」と言われていました。
環境問題は、世代を超えて保全に対する取組を、市民みんなで実践し考えて次の世代までつなぐことが必要だと認識しました。 (市民環境記者 大月)
  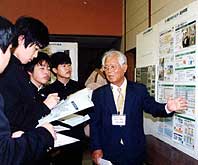 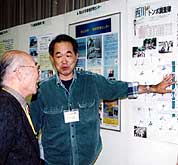 

 岡山市中学・高校環境研究発表会
みんな、豆博士! 岡山市中学・高校環境研究発表会
みんな、豆博士!
11/30(日)午前10時から、環境研究を行っている中・高生の研究成果の発表会がありました。
   
岡山市環境調整課の内藤課長は、「私たちが今、普通に暮らしている積み重ねが50〜100年後に迷惑をかけないよう、環境や生き物の様子を目や体で感じる事が大切です。学校の活動で研究した事を発表・意見交換しましょう」と、生徒たちの緊張をほぐすように挨拶されました。
そして、発表後は岡山大学の大久保先生に講評と助言をいただきました。
関西高等学校理学部化学班のテーマは「旭川の水質-1日の変化を追う」。時間帯による水質の変化を調査し、夜の調査と川の測定場所は苦労があったようです。小河川では朝食時と夕食時に水質が悪化するという結果が出ており、私たちも排水には気をつけないといけません。
岡山県立高松農業高校のテーマは「希少生物保護活動」。絶滅の恐れのあるスイゲンゼニタナゴを校内にあるビオトープ増殖池で調査研究しています。他のグループや学校との交流もあり、お兄さん的存在のように感じました。
岡山県立興陽高校は「藤田の水路の生き物調査ととりくみ」をテーマに、校内を走る水路を活かしてビオトープ池を作ろうとしています。ビオトープ池の先輩「高松農業高校」との交流もあり、ただ今研究中です。田園地帯藤田の周辺にいる生き物を育てて、少しでもきれいな藤田にしようと試みています。
福田中学校理科同好会は理科の好きな生徒たちの集まりで「学区内の水質検査と水生昆虫の顕微鏡撮影」の研究。田んぼに浄化作用があることや、住宅地のフタがけしてある用水にも、思いの他生物がいたことなどに興味がつきないようでした。
発表の後、お互いに質問したり答えたりして、情報交換ができていました。高校生や中学生の発表を聞いていると、自然に親しみながら自然を守る、豆博士のようで将来が楽しみです。(市民環境記者 大月)
 
なぜ12月なの?1997年(平成9年)12月に、国際的な地球温暖化対策を話し合う地球温暖化防止会議(COP3)を京都で開催したことから、地球温暖化防止に向けた行政や事業者、また国民の皆さんの取組を促すために、1998年から毎年12月を「地球温暖化防止月間」に指定し、地球温暖化防止対策を推進しているのです。
|