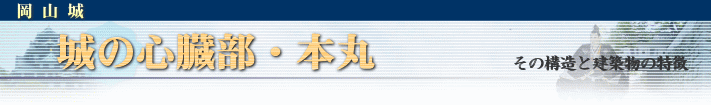| ■三家により異なる石積み |
| 本丸を形作る石垣は、同じ本丸郭内でありながら、場所により石の積み方に大きな違いが見られる。これは宇喜多・小早川・池田の3家による築造の歴史の反映であり、またそれはそのまま石垣築造技術更新の歴史でもある。 |
| ●宇喜多時代 |
| 今に残る石垣のうち、本段部分の大部分は宇喜多秀家による築城時に築かれたもので、自然石をほとんど加工せずそのまま積んだ「野面積み」と呼ばれる手法を用いている。 |
| ●小早川時代 |
| 小早川秀秋2年足らずの在城中、本段の一部改修と、表向の南半分の大幅な改修が行われた。 |
| ●池田時代 |
| 池田時代(忠継以降)には表向北半分の拡張と、下の段の改修が行われた。石垣技術はさらに発達し、成熟期の「打込接」と、石材をあらかじめしっかり加工して隙間なく積み上げる「切込接」と呼ばれる最新技術が用いられている。そのため、表向の段では、南部と北部で石垣の趣が同じ城とは思えないほど異なっている。中の段の西側では、宇喜多時代の野面積み石垣と池田時代の打込接石垣が隣り合っている様子が見られる。 |
>>岡山城本丸探訪へ
(石垣についても詳しく解説) |
|
|
|
| 宇喜多期の石垣(左:天守台石垣、右:本段南東部石垣) |
|
|
小早川期の石垣(左:中の段南西、右:本段東部)
右は真ん中から継ぎ足した跡が見られ、おそらく宇喜多期のものに小早川が手を加えたものと思われる。 |
|
|
| 池田期の石垣(左:月見櫓下、右:廊下門脇) |
|