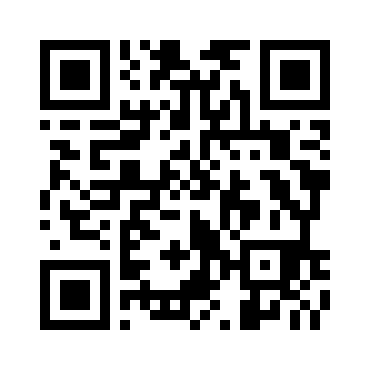出産
妊娠したら
妊娠したら、各保健センター・さんさんステーションなどへ妊娠の届出をしてください。
妊娠・出産・育児の一貫した健康記録として活用する親子手帳をお渡しします。また、保健所・保健センターでは妊娠中の人を対象に健康相談や家庭訪問をしています。(詳しくは妊娠届・親子手帳のページをご覧ください。)
名 称 | 問い合わせ |
|---|---|
親子手帳 | 保健所健康づくり課 |
妊婦相談、妊婦家庭訪問 | 保健所健康づくり課 |
妊産婦一般健康診査助成 | 保健所健康づくり課 |
助産施設への入所 | 各福祉事務所 |
赤ちゃんが生まれたら
赤ちゃんが生まれたら、14日以内に各区役所市民保険年金課、各支所・地域センターなどに「出生届」を出してください。
また、中学3年生までの子どもを養育している人に支給される児童手当や、子ども医療費助成制度があります。
名 称 | 問い合わせ |
|---|---|
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター | |
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター | |
| 各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター | |
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所 | |
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所 | |
出産連絡票(兼低出生体重児出生届) | 保健所健康づくり課 |
こんにちは赤ちゃん訪問
保健所健康づくり課 電話:086-803-1264
岡山市に住民登録した赤ちゃん全員に、研修を受講した地域の愛育委員がプレゼントの「赤ちゃん絵本」を持って訪問します。
子育ての不安や悩みをお聞きしたり、子育ての情報をお届けします。
愛育委員は、子育てを支援する地域のボランティアです。地域のこと、子育てのことなど、気軽に相談してみてください。
赤ちゃん絵本
赤ちゃん絵本の購入事業は、「心豊かな岡山っ子応援団」の取り組みの一つです。
「心豊かな岡山っ子応援団」は、子どもが健やかに育ち、子どもを安心して生み育てることができるまちを築き、社会全体で子育ち・子育てを支えていく機運を醸成することを目的として、家庭・地域・事業者・学校園・行政の代表が集まり、平成19年7月に設置されたものです。
地域子育て支援課 電話:086-803-1224
子育て応援サイト「こそだてぽけっと」

岡山の子育てに関するさまざまな情報を集めたホーム ページを開設しています。
親子で参加できるイベント、困ったときの相談先、各種助成・手当、子育てを支援する施設、子育ての応援をされている皆さんからの活動紹介など、子育てに役立つ情報が、カレンダーや年齢別などの分かりやすい形でまとまっています。
入園・入学
保育園への入園
就園管理課 電話:086‐803‐1432、各福祉事務所・支所
認定こども園への入園
就園管理課 電話:086‐803‐1432、各福祉事務所・支所
地域型保育事業(小規模保育事業所、事業所内保育事業所)の利用
就園管理課 電話:086‐803‐1432、各福祉事務所・支所
幼稚園への入園
各幼稚園、就園管理課 電話:086-803-1432
市立幼稚園は、4歳・5歳児(一部3歳児)を対象に園児を募集していますので、希望園へ入園願を提出してください。私立・国立幼稚園については、各園へお問い合わせください。
小学校・中学校への入学
教育委員会就学課 電話:086-803-1587
市立の小学校・中学校・義務教育学校は居住地で通学する学校が決められていますが、新入学時に一定の条件のもとで隣の学区の中学校を選ぶことができる制度も実施しています。市立の小学校・中学校・義務教育学校は、授業料は不要ですが、給食費や教材費の一部負担が必要です。
小学校・中学校・義務教育学校への入学
小学校に入学する前年の10月に就学時健康診断日の通知を、また1月末に小学校・中学校・義務教育学校に入学する児童・生徒の保護者に就学通知書を送ります。以下の場合は早めに教育委員会就学課へ連絡してください。
- 就学通知書が届かない、内容に誤りがある場合
- 病気その他の理由で就学が困難である場合
- 身体が非常に弱い、手足・目・耳が不自由な場合
- 外国籍だが市立小・中学校・義務教育学校への就学を希望する場合
小学校・中学校・義務教育学校の転校
市内転居:学校から転校の書類を受け取り、転居手続きと同時に、転校の手続きをしてください。
市外転出:学校から転校の書類を受け取り、転入先の教育委員会の指示を受けてください。
高等学校などへの入学
こども福祉課 電話:086-803-1221
奨学金の給付(返済不要)
経済的理由により高等学校などの修学が困難な人に返済不要の奨学金を給付します。募集期間は毎年8月から9月で、年間6万円(通信制高校は37,000円)です。詳細は岡山市給付型奨学金のページでご確認ください。
子どもの健康
乳幼児健康診査
保健所健康づくり課 電話:086-803-1264
乳児健康診査
(乳児一般健康診査・3カ月から5カ月児健康診査)
県内のどこの医療機関でも受診できます。
7カ月・8カ月児健康診査
市内の指定医療機関でのみ実施。健診料の半額を市が負担します。
1歳6カ月児健康診査・3歳児健康診査
1歳6カ月、3歳6カ月の子どもを対象に、小児科健診・歯科検診、栄養相談、育児相談、保健相談などの総合健康診査を各保健センターで実施しています。
離乳食講習会
各保健センター
離乳食の作り方の実演と離乳の進め方についての講習です。
歯と口の健康相談
各保健センター
歯科医師・歯科衛生士による歯と口の相談を行います(年3回・無料)。日程は広報紙または「歯と口の健康相談」を参照。
予防接種
感染症対策課 電話:086-803-1262
市が無料で実施する予防接種は、子どものBCG、四種混合、三種混合、二種混合、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、ロタウイルスです。
なお、予防接種手帳は、出生届出の翌月に郵送します。
小児救急医療電話相談
電話:#8000または 電話:086-801-0018
子どもの夜間の急な発熱、けいれんなど具合が悪くなったときの対処方法などについて、看護師などが電話で相談に応じるとともに、医療機関への受診について適切なアドバイスを行います。
児童手当
こども福祉課 電話:086-803-1222
15歳(中学3年生)に達した最初の3月31日までの児童を養育している保護者に支給します。
子ども医療費助成
医療助成課 電話:086-803-1219
健康保険に加入している子どもが医療機関等で受診した場合、保険診療の自己負担分の全部または一部を助成します。