
今回は、マラソンランナーでオリンピックメダリストの有森裕子さんが代表理事を務める同NPO法人にお伺いし、設立のきっかけや理念、今まで行ってきた活動について、事務局長の田代邦子さんと事業部の井上恭子さん、広報の山本雅之さんにお話を聞いてきたよ。
「アンコールワット国際ハーフマラソン」からスタート
のっぷ:初めまして、「つながる協働ひろば」ののっぷです。
ハート・オブ・ゴールドさんは、被災地や紛争地で苦境に陥っている子どもや障がい者、貧困層の人々に対する支援を行っているそうですが、活動を始めたきっかけは何だったんですか。
田代さん:1996年にカンボジアで初めて開催されたチャリティーマラソン「アンコールワット国際ハーフマラソン」に代表の有森がゲストランナーとして呼ばれたことがきっかけです。
この大会は、地雷廃絶と地雷被害者の救済、子どもの健康改善支援のためにスタートしたのですが、有森が現地の惨状を見てこの活動は続けるべきだと感じたそうです。そのためには、個人ではなく組織で支援していく必要があるということに気づき、この団体を立ち上げました。

アンコールワット国際ハーフマラソン
この国際マラソンにおいては、競技、資金調達、参加者の募集や広報などあらゆる運営の支援をするとともに、将来カンボジアの人たちの力だけで国際大会の開催が可能になるよう、現地スタッフの育成にも力を注ぎました。
結果、第18回大会からはすべての運営をカンボジア側に移譲。最初は参加者645人、参加国16か国からスタートした大会も今では参加者1万人以上、参加国も80か国を越えました。これに伴い観光客も増え経済面でも成果があり、スポーツイベントの果たす役割が認知されるようになりました。体育教育と自立支援が活動の柱
のっぷ:カンボジアの子どもの体育科教育においても大切な役割を果たしてきたそうですが、どんな活動をしているのですか?
田代さん:カンボジアでは、ポルポト政権によりスポーツ施設の破壊や、指導者や選手の虐殺が行われたため、子どもの体育科教育がほとんどできない状態が続いていました。
この状況を改善したい、と2001年から始めたのが「青少年・指導者育成スポーツ祭」です。これは小学生を対象にサッカーやバレーなどの指導をするもので、2度目からは指導者育成もスタートさせました。プログラムの中にエイズ教育や地雷の被害を受けないための教育も入れ込むようにした結果、体育科教育がスポーツ技術を伸ばすだけでなく、子ども達の健やかな成長に役に立つことがカンボジアの教育省にも理解されるようになりました。

イスを並べて平均台の授業
井上さん:「青少年・指導者育成スポーツ祭」を当団体の運営で5年間行った後、2006年からは教育省と連携して事業内容を体育科教育へ移行しました。小学校の体育指導要領を作って、それに基づいた指導書作成にも着手。全国でモデル校を指定し、100校ほどで新しい体育を実施。現在教育省が普及を進めている状態です。
その後、中学校でも指導要領・指導書を作成して普及に入っています。高校ではそれに合わせて、教育省が主体的に指導書を作り始めました。私たちはそのサポートもしています。小学校の指導書には、「OKAYAMAに感謝します」というカンボジア教育省からの謝辞が入っているんですよ!
カンボジアの教員への体育科研修会
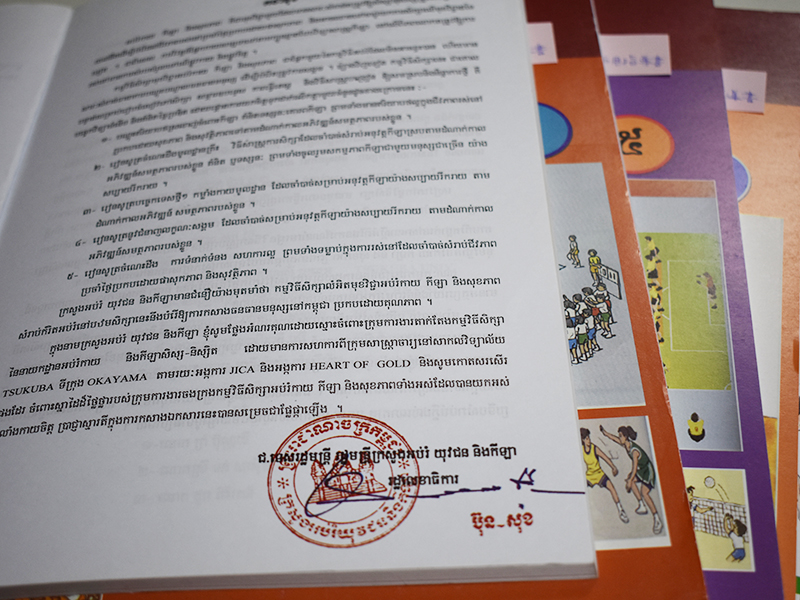
指導書には「OKAYAMA」の文字が
のっぷ:少しずつ整備していって、今はカンボジアの方の力で広がりつつあるんですね。
他にも何か活動をされていますか?
田代さん:何か与えて終わりという一時的な支援ではその場限りにしかならないので、これからカンボジアを担っていく子どもに向けた支援活動を行っています。
日本語を学んで仕事につなげたいと考える子どもに向けた日本語教室を開講しました。
また、孤児などが安心して生活できる環境のなかで自立していけるよう、ニューチャイルド・ケア・センター(NCCC)という養護施設も運営しています。ハート・ペアレント事業として、入所している子どもを日本から里親として継続して支援する仕組みも作りました。現在、岡山の学校との交流も盛んに行われています。
岡山とカンボジア、岡山での活動

支援した学校名がついているマット
のっぷ:岡山の学校とカンボジアがどのように繋がるんですか?
田代さん:岡山市はハート・オブ・ゴールドの活動に先生を派遣しており、数多くの方がカンボジアで指導にあたっています。これは、全国的にもめずらしい取組なんですよ。
現地に入った先生からは、視野が広がり得るものが多かったという声を多数いただいています。
また、帰国した先生が、カンボジアで懸命に生きる子どもたちの姿を語り伝えることで、岡山の学校・子ども達にも支援活動の輪が広がるとともに、国際理解の素養を育むことに繋がっています。
のっぷ:わぁ、すごい!自分たちの活動が目に見える形になると、子ども達もうれしいですよね。
岡山県内での活動も盛んなのでしょうか?
山本さん:毎年、玉野のおもちゃ王国で親子チャリティーマラソンを開催し、みなさんの参加費でカンボジアの小学校に鉄棒を設置しています。また、平成30年7月豪雨の際には、総社市で「チャリティーリレーマラソンinそうじゃ」を開催し、収益を総社市の復興に役立てていただきました。

親子チャリティーマラソンinおもちゃ王国

チャリティーリレーマラソンinそうじゃ
パートナーとして共に育っていく
のっぷ:これからの抱負を教えてください。
田代さん:小学校、中学校、高校へと続いてきたカンボジアの体育科教育の流れがありましたが、いまは教員養成のための4年制体育大学の開学準備を進めています。
国際協力は、豊かなところが貧しいところを助けるという姿勢ではなく、パートナーとしてお互いが育っていかなければ続けられません。有森自身がこの活動を通じて学んだことが多かったことから、共に育つ「共育」という、わたしたちの理念が生まれたのだと思います。
もちろん開発途上国の子だけが大事なのではなくて、日本の子ども達にも健やかに育ってほしいと願っています。国際交流、国際教育の一環として、学校の先生たちと一緒に今後も子ども達に少しでもプラスになる活動を続けていきたいですね。

(左から)山本さん、田代さん、井上さん

「現地の人が希望と勇気をもって立ち上がろうとするきっかけづくりを、スポーツや教育を通じて行っていきたい」という田代さんのお話が、心に残ったよ。
相手の立場に立って活動をすることで、支援する・されるという関係ではなく、「共に育つ(学び合う)」ことができるんだね。

20年以上も活動を続けているハート・オブ・ゴールドさん。
「できる人が、できる事を、できる限り」。
一人一人の力は小さくても、合わせると大きな力になるよね。
私にできることって何だろう?
関連リンク
NPO法人ハート・オブ・ゴールド
- 住所:岡山市北区西辛川895-7 レジデンスアロー101号
- 連絡先:電話番号:086-284-9700

ありがとうございました。次はどちらの法人におじゃましようかなぁ。
